すえなが内科在宅診療所
(在宅療養支援診療所)
あなたに安心とやすらぎを提供します。
住み慣れた我が家での生活を支えます。
すえなが内科在宅診療所
(在宅療養支援診療所)
あなたに安心とやすらぎを提供します。
住み慣れた我が家での生活を支えます。
すえなが内科在宅診療所
(在宅療養支援診療所)
あなたに安心とやすらぎを提供します。
住み慣れた我が家での生活を支えます。
診療のご案内
医療理念
病む患者・家族のつらさに寄り添い、ひとり一人のいただいた使命を全うされ、住み慣れた地域で、住み慣れた自宅で過ごすことが出来るような治療・ホスピス・緩和ケアの提供を行います。
ご利用方法
1) まずは、お気軽に電話でご連絡下さい
電話: 083−902−5300
病状や病気の悩みなどについてお尋ねします。
初回相談の日程をご予約します。
(お急ぎの場合は24時間対応します。)
2) 初回の相談にお越しください。状況によっては、直接、自宅、施設、病院までお伺い致します。
医師や医療相談員により初回相談を行います。
患者さん本人が同席されなくても結構です。ご家族、友人の相談でも構いません。
主治医の紹介状があればお持ちください。
診療所に来れない場合は、自宅や施設に直接伺います。
3) 訪問診療開始いたします
初回相談をふまえて、定期的な訪問診療や、薬の処方などを開始します。
ご利用対象
1) がん全般(早期から終末期まで) いつの時期でも良いです
2) がんの多彩な症状に苦しまれている方(がん性疼痛、呼吸困難、食欲不振、全身倦怠感、腹水、腸閉塞、浮腫、不眠、せん妄等)
3) 脳梗塞後遺症
4) 寝たきり
5) 神経難病
6) 認知症
7) その他、外来通院が困難な方すべて
自宅(あるいは施設)で、在宅療養を希望する方はどなたでもご利用できます。ご連絡下さい。また、24時間365日、電話連絡体制を取っています。病状に応じ、緊急訪問も行っています。
診療内容
外来診療(午前中)
一般内科診療
がん治療(抗がん剤の休眠療法、ホルモン療法、ゾメタなど)
がんの症状緩和治療
在宅診療(午後)
外来通院が困難な方すべて
1) 点滴、注射や輸血など
2) 在宅酸素、人工呼吸器などの呼吸管理
3) IVH(皮下埋め込み)中心静脈栄養の管理(持続投与)
4) がん性疼痛:モルヒネ持続皮下注射の管理
5) 胃瘻PEGや経鼻栄養カテーテル管理
6) 尿カテーテル、膀胱瘻、腎瘻
7) 人工肛門、腸瘻の管理
8) 気管切開管理・吸引
9) 褥創処置、外科的処置など
診療範囲
山口市全域(概ね当診療所より車で30分以内圏内)です。
圏外でも状況に応じて対応できることがあります。お気軽にご相談ください。
診療指針
すえなが内科在宅診療所は、一般の外来はもちろん、がん患者の苦痛緩和を中心に、外来、在宅における治療、ケアを行います。
内科疾患に関して外来にて治療、相談を行います。
がん相談、セカンドオピニオンを行います。
外来通院が難しく、自宅や入所施設での生活を望まれる方には在宅診療、往診を定期的に行います。
在宅療養支援診療所として在宅支援に向けて諸機関と連携して、訪問診察・往診の形で医療面から患者・家族を支えます。
*あらゆる悪性腫瘍(がん)以外の種々の病気で苦しんでいる方や困っている方が最も住み慣れた自宅や施設で安心して、ゆっくり過ごせるような在宅医療を提供します。
*定期的に自宅へ訪問診察し、緊急時には24時間、365日対応します。
認定研修施設
当診療所は、日本緩和医療学会認定研修施設(認定番号:20142016号)として認定されています。

診療のご案内
医療理念
病む患者・家族のつらさに寄り添い、ひとり一人のいただいた使命を全うされ、住み慣れた地域で、住み慣れた自宅で過ごすことが出来るような治療・ホスピス・緩和ケアの提供を行います。
ご利用方法
1) まずは、お気軽に電話でご連絡下さい
電話: 083−902−5300
病状や病気の悩みなどについてお尋ねします。
初回相談の日程をご予約します。
(お急ぎの場合は24時間対応します。)
2) 初回の相談にお越しください。状況によっては、直接、自宅、施設、病院までお伺い致します。
医師や医療相談員により初回相談を行います。
患者さん本人が同席されなくても結構です。ご家族、友人の相談でも構いません。
主治医の紹介状があればお持ちください。
診療所に来れない場合は、自宅や施設に直接伺います。
3) 訪問診療開始いたします
初回相談をふまえて、定期的な訪問診療や、薬の処方などを開始します。
ご利用対象
1) がん全般(早期から終末期まで) いつの時期でも良いです
2) がんの多彩な症状に苦しまれている方(がん性疼痛、呼吸困難、食欲不振、全身倦怠感、腹水、腸閉塞、浮腫、不眠、せん妄等)
3) 脳梗塞後遺症
4) 寝たきり
5) 神経難病
6) 認知症
7) その他、外来通院が困難な方すべて
自宅(あるいは施設)で、在宅療養を希望する方はどなたでもご利用できます。ご連絡下さい。また、24時間365日、電話連絡体制を取っています。病状に応じ、緊急訪問も行っています。
診療内容
外来診療(午前中)
一般内科診療
がん治療(抗がん剤の休眠療法、ホルモン療法、ゾメタなど)
がんの症状緩和治療
在宅診療(午後)
外来通院が困難な方すべて
1) 点滴、注射や輸血など
2) 在宅酸素、人工呼吸器などの呼吸管理
3) IVH(皮下埋め込み)中心静脈栄養の管理(持続投与)
4) がん性疼痛:モルヒネ持続皮下注射の管理
5) 胃瘻PEGや経鼻栄養カテーテル管理
6) 尿カテーテル、膀胱瘻、腎瘻
7) 人工肛門、腸瘻の管理
8) 気管切開管理・吸引
9) 褥創処置、外科的処置など
診療範囲
山口市全域(概ね当診療所より車で30分以内圏内)です。
圏外でも状況に応じて対応できることがあります。お気軽にご相談ください。
診療指針
すえなが内科在宅診療所は、一般の外来はもちろん、がん患者の苦痛緩和を中心に、外来、在宅における治療、ケアを行います。
内科疾患に関して外来にて治療、相談を行います。
がん相談、セカンドオピニオンを行います。
外来通院が難しく、自宅や入所施設での生活を望まれる方には在宅診療、往診を定期的に行います。
在宅療養支援診療所として在宅支援に向けて諸機関と連携して、訪問診察・往診の形で医療面から患者・家族を支えます。
*あらゆる悪性腫瘍(がん)以外の種々の病気で苦しんでいる方や困っている方が最も住み慣れた自宅や施設で安心して、ゆっくり過ごせるような在宅医療を提供します。
*定期的に自宅へ訪問診察し、緊急時には24時間、365日対応します。
認定研修施設
当診療所は、日本緩和医療学会認定研修施設として認定されています。

✕
診療のご案内
医療理念
病む患者・家族のつらさに寄り添い、ひとり一人のいただいた使命を全うされ、住み慣れた地域で、住み慣れた自宅で過ごすことが出来るような治療・ホスピス・緩和ケアの提供を行います。
ご利用方法
1) まずは、お気軽に電話でご連絡下さい
電話: 083−902−5300
病状や病気の悩みなどについてお尋ねします。
初回相談の日程をご予約します。
(お急ぎの場合は24時間対応します。)
2) 初回の相談にお越しください。状況によっては、直接、自宅、施設、病院までお伺い致します。
医師や医療相談員により初回相談を行います。
患者さん本人が同席されなくても結構です。ご家族、友人の相談でも構いません。
主治医の紹介状があればお持ちください。
診療所に来れない場合は、自宅や施設に直接伺います。
3) 訪問診療開始いたします
初回相談をふまえて、定期的な訪問診療や、薬の処方などを開始します。
ご利用対象
1) がん全般(早期から終末期まで) いつの時期でも良いです
2) がんの多彩な症状に苦しまれている方(がん性疼痛、呼吸困難、食欲不振、全身倦怠感、腹水、腸閉塞、浮腫、不眠、せん妄等)
3) 脳梗塞後遺症
4) 寝たきり
5) 神経難病
6) 認知症
7) その他、外来通院が困難な方すべて
自宅(あるいは施設)で、在宅療養を希望する方はどなたでもご利用できます。ご連絡下さい。また、24時間365日、電話連絡体制を取っています。病状に応じ、緊急訪問も行っています。
診療内容
外来診療(午前中)
一般内科診療
がん治療(抗がん剤の休眠療法、ホルモン療法、ゾメタなど)
がんの症状緩和治療
在宅診療(午後)
外来通院が困難な方すべて
1) 点滴、注射や輸血など
2) 在宅酸素、人工呼吸器などの呼吸管理
3) IVH(皮下埋め込み)中心静脈栄養の管理(持続投与)
4) がん性疼痛:モルヒネ持続皮下注射の管理
5) 胃瘻PEGや経鼻栄養カテーテル管理
6) 尿カテーテル、膀胱瘻、腎瘻
7) 人工肛門、腸瘻の管理
8) 気管切開管理・吸引
9) 褥創処置、外科的処置など
診療範囲
山口市全域(概ね当診療所より車で30分以内圏内)です。
圏外でも状況に応じて対応できることがあります。お気軽にご相談ください。
診療指針
すえなが内科在宅診療所は、一般の外来はもちろん、がん患者の苦痛緩和を中心に、外来、在宅における治療、ケアを行います。
内科疾患に関して外来にて治療、相談を行います。
がん相談、セカンドオピニオンを行います。
外来通院が難しく、自宅や入所施設での生活を望まれる方には在宅診療、往診を定期的に行います。
在宅療養支援診療所として在宅支援に向けて諸機関と連携して、訪問診察・往診の形で医療面から患者・家族を支えます。
*あらゆる悪性腫瘍(がん)以外の種々の病気で苦しんでいる方や困っている方が最も住み慣れた自宅や施設で安心して、ゆっくり過ごせるような在宅医療を提供します。
*定期的に自宅へ訪問診察し、緊急時には24時間、365日対応します。
認定研修施設
当診療所は、日本緩和医療学会認定研修施設として認定されています。

院長挨拶

ご挨拶
私は山口市仁保の生まれで、1979年より34年間綜合病院山口赤十字病院にて内科、緩和ケア科に勤務し、長い年月、一般内科、消化器内科の疾患、がんの診断、治療から緩和ケアを必要とする様々ながんの症状緩和を専門として診療し、つらい患者さんやご家族に寄り添って参りました。1992年から緩和ケア病床を立ち上げ、入院患者のみならず、在宅に出かけて在宅医療を行って参りました。
一般内科疾患の診断治療、がんに伴う様々な症状緩和を外来にて行います。
また、緩和ケアを必要とするがんの在宅ホスピスケアや病気の重い患者さんで通院困難な方で、在宅での医療処置の多い患者様の受け入れもできます。病状の重い方、今後悪化する可能性のある方でもご安心ください。
一般内科、消化器内科にも携わってきましたのでがん以外の疾患(脳梗塞後遺症、慢性呼吸不全、寝たきり、神経難病、認知症など)も在宅での治療・ケアを行います。
多くの医療機関や病院、医師、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所などとの連携を行ってきました。がんやがん以外の病気でお悩みの患者さんや家族の方は お気軽にご相談下さい。いつでも相談を承ります。
すえなが内科在宅診療所 院長 末永和之
略歴
末永和之
山口市仁保出身 山口高等学校卒業
1974年 鳥取大学医学部卒業
1978年 鳥取大学大学院医学研究科終了(医学博士)
1979年 綜合病院山口赤十字病院内科副部長
1995年 ドイツ・フランスのホスピス・緩和ケア視察
1996年 内科部長
2001年 緩和ケア科部長
2009年 副院長
2013年 すえなが内科在宅診療所開設
日本緩和医療学会暫定指導医
NPO日本ホスピス緩和ケア監事
日本死の臨床研究会顧問
山口大学医学部非常勤講師
山口県立大学非常勤講師
日本在宅ホスピス研究会会員
日本緩和医療学会会員
日本内科学会会員
日本音楽療法学会会員
日本統合医療学会会員
山口県緩和ケア研究会世話人
院長挨拶

ご挨拶
私は山口市仁保の生まれで、1979年より34年間綜合病院山口赤十字病院にて内科、緩和ケア科に勤務し、長い年月、一般内科、消化器内科の疾患、がんの診断、治療から緩和ケアを必要とする様々ながんの症状緩和を専門として診療し、つらい患者さんやご家族に寄り添って参りました。1992年から緩和ケア病床を立ち上げ、入院患者のみならず、在宅に出かけて在宅医療を行って参りました。
一般内科疾患の診断治療、がんに伴う様々な症状緩和を外来にて行います。
また、緩和ケアを必要とするがんの在宅ホスピスケアや病気の重い患者さんで通院困難な方で、在宅での医療処置の多い患者様の受け入れもできます。病状の重い方、今後悪化する可能性のある方でもご安心ください。
一般内科、消化器内科にも携わってきましたのでがん以外の疾患(脳梗塞後遺症、慢性呼吸不全、寝たきり、神経難病、認知症など)も在宅での治療・ケアを行います。
多くの医療機関や病院、医師、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所などとの連携を行ってきました。がんやがん以外の病気でお悩みの患者さんや家族の方は お気軽にご相談下さい。いつでも相談を承ります。
すえなが内科在宅診療所 院長 末永和之
略歴
末永和之
山口市仁保出身 山口高等学校卒業
1974年 鳥取大学医学部卒業
1978年 鳥取大学大学院医学研究科終了(医学博士)
1979年 綜合病院山口赤十字病院内科副部長
1995年 ドイツ・フランスのホスピス・緩和ケア視察
1996年 内科部長
2001年 緩和ケア科部長
2009年 副院長
2013年 すえなが内科在宅診療所開設
日本緩和医療学会暫定指導医
NPO日本ホスピス緩和ケア監事
日本死の臨床研究会世話人代表
日本緩和医療学会代議員
山口大学医学部非常勤講師
山口県立大学非常勤講師
日本在宅ホスピス研究会会員
日本内科学会会員
日本音楽療法学会会員
山口県緩和ケア研究会世話人
図書コーナー
ひとひらの死
いのちの響 〜ホスピスの春夏秋冬〜

ゆうにゆうにまあるくまあるく

笑薬
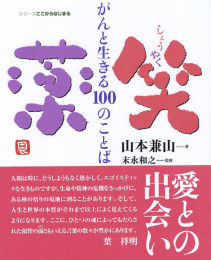
ぼくが生きるということ
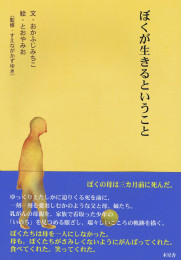
✕
院長挨拶

ご挨拶
私は山口市仁保の生まれで、1979年より34年間綜合病院山口赤十字病院にて内科、緩和ケア科に勤務し、長い年月、一般内科、消化器内科の疾患、がんの診断、治療から緩和ケアを必要とする様々ながんの症状緩和を専門として診療し、つらい患者さんやご家族に寄り添って参りました。1992年から緩和ケア病床を立ち上げ、入院患者のみならず、在宅に出かけて在宅医療を行って参りました。
一般内科疾患の診断治療、がんに伴う様々な症状緩和を外来にて行います。
また、緩和ケアを必要とするがんの在宅ホスピスケアや病気の重い患者さんで通院困難な方で、在宅での医療処置の多い患者様の受け入れもできます。病状の重い方、今後悪化する可能性のある方でもご安心ください。
一般内科、消化器内科にも携わってきましたのでがん以外の疾患(脳梗塞後遺症、慢性呼吸不全、寝たきり、神経難病、認知症など)も在宅での治療・ケアを行います。
多くの医療機関や病院、医師、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所などとの連携を行ってきました。がんやがん以外の病気でお悩みの患者さんや家族の方は お気軽にご相談下さい。いつでも相談を承ります。
すえなが内科在宅診療所 院長 末永和之
略歴
末永和之
山口市仁保出身 山口高等学校卒業
1974年 鳥取大学医学部卒業
1978年 鳥取大学大学院医学研究科終了(医学博士)
1979年 綜合病院山口赤十字病院内科副部長
1995年 ドイツ・フランスのホスピス・緩和ケア視察
1996年 内科部長
2001年 緩和ケア科部長
2009年 副院長
2013年 すえなが内科在宅診療所開設
日本緩和医療学会暫定指導医
NPO日本ホスピス緩和ケア監事
日本死の臨床研究会世話人代表
日本緩和医療学会代議員
山口大学医学部非常勤講師
山口県立大学非常勤講師
日本在宅ホスピス研究会会員
日本内科学会会員
日本音楽療法学会会員
山口県緩和ケア研究会世話人
図書コーナー
ひとひらの死
いのちの響 〜ホスピスの春夏秋冬〜

ゆうにゆうにまあるくまあるく

笑薬
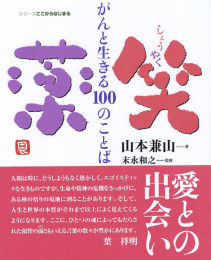
ぼくが生きるということ
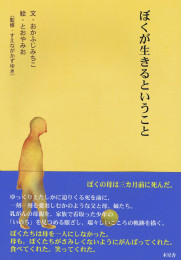
院長 コラム
家がええ
ナラやクヌギの若葉が萌えいずる山道を、私の愛車のポンコツホンダライフに乗って、今日も午後在宅の患者さんの家に出かける。
「どうですか」
「息がえらく、あまり動けないね。どうにかトイレに行っているも、息が弾み、布団に戻ると左向きでどうにかじっとしているんじゃ」
彼は、2年半、大腸がんの術後、抗癌剤の治療などをしていたが、4月にとても息が苦しくなり、急遽かかりつけの先生を尋ねた。胸の写真を撮ってもらうと、左胸には胸水が大量に溜まり、息ができない状態であった。私に紹介があり、診察して、
「今から外来で胸の水を抜いて上げましょう。楽になりますよ」
その場でエコーをして処置室にてエコー下で胸水穿刺を行い、1500mlの胸水を抜いて、
「息が楽になったでしょう」
「ああ、随分息が楽になった。まるで先ほどの苦しさが嘘みたい。先生が神様にみえる。ああ、本当に楽だな」
「それは良かった。お家で過ごしたいですか。入院しますか」
「家がええなあ」
「自宅にすぐ酸素を入れて上げましょう。在宅酸素といって、自宅で空気中の酸素を取り出し、濃縮して吸うことができる安全な器械があり、業者に伝えますので、すぐに家にもって行ってもらい、設置してもらいましょう。自宅で安心して過ごすために24時間対応してくださる訪問看護師さんを紹介しましょう。
自宅で困ったことがあったり、不安であったり、医療的、看護的なことが起こればすぐに電話連絡が付き、自宅で安心して過ごす事ができますよ。これからは私の方から家に出向いて診察し、また胸の水を抜く必要があれば抜いてあげましょう。家での生活を大切にしましょうね。」
「ああ、良かった。また入院かと思ったら本当に嫌だなと思ったんじゃ」
数日後に、小さなエコーの器械を携えて、お宅を尋ねた。
西日の当たるお部屋でお布団に寝て横になっておられた。奥さんと二人住まいであった。
「その後、どうですか」
「家に帰って、酸素を吸って、訪問看護師さんに来てもらい、楽に過ごしていたんじゃ。昨日ぐらいからトイレにいくのに少し息苦しくなって来ちょった。布団に横になるのが一番楽だな。」
「今の目標や希望は、何ですか」
「自分は趣味で竹細工をしている。竹籠などをたくさん作って、皆にあげるのが一番嬉しい。今でも私の作った竹籠を待っておられる人がたくさんおられる。早く、元気になって竹籠を編んであげるんじゃ。秋祭りまでにはそれをせんとな」
「そうですね、自分の趣味が活かされ、喜んでもらえたり、お役に立てることが一番の生きることの力になりますね。胸の水を診てみましょう」
エコーで胸の水を観ると、また溜まっている状態であった。胸水穿刺の道具を持参していたので、自分一人で清潔に対応してエコー下で穿刺を行った。
畳の上に敷いた布団に寝ておられるので、穿刺のチューブから出る胸水を平べったい器を奥さんに持ってきてもらい、その中に排液した。
「家での生活はどうですか。布団では立ち上がりなどが次第に難しくなるけど、ベッドなどにするとトイレにいくのも比較的立ち上がりやすく便利ですが、入れてあげましょうか」
「いや、今までの生活が布団なので、このままでええ。布団だとゴロンところがると、暖かい日差しのあるところにすぐいけるからね」
「そうだね、自分のペースが一番いいよね。ところで、これからまた入院する気持ちはあるかね」
「いや、先生と訪問看護おかふじさんに来てもらったら、入院する気は全くないよ。これまでの2年半、治療治療でとってもきつかった。えらいばっかりでちっともええことがなかった。治療で治るかと思うから受けてきたけど、こんな状態になって、ひとつも楽じゃあない。看護師さんも優しいと聞いていたがちっとも優しくなかった。自由もなく制限ばかりで狭いベッドで我慢ばかりしていた。治ると思ったから受けてきたのに・・・」
「そうでしたか。我慢ばっかりでしたか。我慢しても完全に治ることがわかれば我慢もできますよね。看護師さんは優しくなかったですか。そうですか。がんが再発したり、進行した場合には完全に治ることは難しくなってきますね。それからの治療は少しでも病気が進行することを抑えことが目的になるので、治りきらないということをしっかり踏まえた上で、自分ではどんな治療の受け方をするかが大切になりますね。その為には生活の目線、自分ではどうしたいかという自己決定、そしてただ単に身体的な延命というよりより良く生きるという、そのような視点を持つことがとても大切になりますよ。臨床の場では医師は画像と、数値と治療の話が中心となり、生活の目線などが抜け落ちた説明がなされることが多いいと思いますね。
ところで、趣味の竹籠が作れるようになれるといいですね。」
「ほんにそうじゃ、皆がわしの竹籠を重宝して使ってくれている。嬉しいもんじゃ」
「皆、希望につなげて、前を向いていくことですね。先はわからんから、今が一番大事で、今を生きることですよね。その為には苦しみがないことですよね」
「訪問看護師さんや先生が来るとそれだけで、安心じゃ」
今日も13万キロ走行した愛車のポンコツホンダライフは快走して家々を回っている。
もう良いよといえる生き方終え方
2013年4月に山口市鰐石町に「すえなが内科在宅診療所」を開設して2年が過ぎた。自分のライフワークを続けるために自分のいただいた使命を果たすために年齢を顧みず外来、在宅診療を行うために診療所を開設した。
新規開業して午前中一般内科診療、がん相談、午後在宅診療の形で診療してきた。診療所の医療理念は病む患者・家族のつらさに寄り添い、ひとり一人のいただいた使命を全うされ、住み慣れた地域で、住み慣れた自宅で過ごすことが出来るような治療・ホスピス・緩和ケアの提供を行うことである。
2年間で在宅診療を行って自宅で最期まで自分の人生を生き抜いていかれ、家族に見守られて人生を終えられた方が118名、自宅で過ごせない方でホームにて介護の皆さんに大切にされ看取られた方が15名、途中で家族の希望や本人の意志で医療機関に入院されて亡くなられた方が46名であった。昼夜を問わず緊急に往診した回数は1078回、訪問診療は5753回であった。
救命救急と違って、現代の医療をもってしても回復できない場合に、自分の最終章をどのような形で締めくくっていくかは、とても大切なことである。自宅での生活の中で、医療管理されない中で家族と向き合い、自分の人生に二重丸を付けて終えていくことは可能なのである。患者と家族を支え、きちんとした看護、介護、医療、福祉サービスが連携して取り組めば可能である。日常生活を阻害する苦しみは取り除き、日常生活を阻害する医療は行わないことが大切で、自宅で最期まで過ごせるのだという情報を知り、自己決定の中で、家族がその意志を尊重することが大切である。私たちは今を生きることの大切さに気づくことである。
私は大學卒業後、6年間法医学にてあらゆる自殺、他殺、不慮の事故、死因不明の死を見つめ、検案、解剖を行い死者の人権を守る仕事をしてきた。その時、感じたことはいのちの終焉は畳の上で家族に見守られて終わりたいと考え、社会病理の不条理を感じた。1990年に一人のがん患者と出会い、ホスピスの道を歩み始めた。多くのがん患者・ご家族と接してきた。その学びの中で感じたことを述べてみたい。
無限の世界から生命をいただき、有限な世界を生き、そしてまた無限の世界に還らなければいけない。医療や人間の力では及ばなくなってくる。看取り看取られるということはその人の全人生を看取り看取られるということである。そして、誰しも避けて通れない死は全て平等である。この世に生をいただいたひとり一人が精一杯生き抜いている。それぞれの固有の歴史、価値観、人生観、死生観などがあり、人生を生き抜いた地域の文化や、家庭環境、生活歴、教育歴、趣味などすべてが異なっている。しかし、すべての人は光るものをもっている。人生二度なし、人生無駄なしと考える。私はひとり一人が天から頂いた使命があると考える。二度とない人生をどのように生きるかは自分の人生の歩み方にかかると思う。ある25歳の癌でなくなった青年は「自分で生まれたくて、生まれてくるやつなんていない。親や境遇を選んで生まれることなんかできない。死にたくなくたって死はすべての人にかならず訪れる。生と死は暴力だ。誰も逆らうことなんてできやしない。だが生と死の間つまり自分の人生をどう生きるのかは自由だ。生きてくれ何があっても生きぬいてくれそして、どんな時でも自分が幸せになろうということをあきらめないでくれ」と言って旅だった。
私は人間社会の相対世界に行き詰まった時、絶対世界に向き合い、自分が何のために此の世にいのちをいただいたかを考えてみることがとても大切であると思う。私の人生モットーはハングリー精神(いつまでもあくなき探究心が生まれる)、感謝(謙虚さ)は有難うという合掌の世界へ通じる、興味をもつこと(試練も苦にならない)、そしてリフレッシュ(心の切り替え)が大切と考える。老いるということは、すべての人がかならず歩む道であり、自らの死から目をそらさず、日頃から自分の人生の最終章を如何に過ごし終えていくかを考えることはとても大切だと思う。ある患者は「死は人生の終末ではない。生涯の完成である」と言っている。私は自分の使命を全うして、そして「もう良いよといえる生き方をして、自分の人生を生き抜いて逝くことを願っている。
多くの人びとが生命を脅かす疾患に直面したとき、患者もご家族も同じ苦しみに見舞われる。特にがんと診断されたときから、患者さんもご家族も心はゆらぎの連続である。がんの進行や再発の不安を抱えながら、希望を見いだしたいと思いながら、日々の療養を続けておられる。身体的な苦しみがあると希望は見いだされなくなる。また、ご家族のこと経済的なことにも思い悩まれる。ご家族もその苦しみは同じなのである。治ってほしい、元気でいてほしいと願い続けられる。そして、実存の喪失、魂のさけびがいつも不安となって頭をもたげてくる。いつまで生きられるのだろうかという将来への希望が見いだせなくなり、愛する家族や人生をともに歩んだ人と別れなければならないという不安、そして自分で自分のことができなくなり、この世にいただいた「いのちの存在」そのものに向きあわざるをえなくなる。その時私たちは何ができるのでしょうか。悩まれ苦しみにある患者さんやご家族の方の足下にそっと灯りをかざすことではないでしょうか。温かい心の通い合いであり、患者さんとご家族の不安に寄り添い、薄明るい歩むべき道筋が見えてくるように傍らに立つことではないでしょうか。ホスピスは悪くて、だめだから行く最後の場ではなく、その瞬間までより良く生きる場であり、患者さんとご家族を支え、橋渡しをする場であると思う。辛さを受け入れていくことはとても時間がかかる。一つ一つの希望が少しずつ削ぎ落とされていく。これを自分で受け止めて行くにはとても時間がかかるものである。受け入れられなく、諦めになっていくことも多くある。患者さんの苦しみに寄り添われるご家族には共に過ごす時間と空間がとても大切な場になるのである。ご家族の悲嘆が大きくならないように患者さんとご家族のこころの架け橋がとても大切だと思う。そして、ホスピスの場は患者さんがその瞬間まで生ききられ、寄り添われる家族はそのいのちを通じて生きるということを考え、乗り越えて、いただいた自らのいのちを生きるということを学ばれる場だと思う。そして、患者さんやご家族が辛いときに辛いと言え、孤独にしないように寄り添って行くことが問われていると思う。その瞬間まで自分のいただいた人生に意味を見いだされ、納得できるように、また安心して後に託すことができるような寄り添いと架け橋を大切にした、そのようなホスピスでありたいと思う。
在宅の良さは医療目線にならない、生活の中での存在であり、管理からの脱却であると考える。多くのチームの協働により、患者・家族に寄り添い、生きる希望を見出し、その瞬間まで自立を支援し、皆様の尊厳性を大切にした関わりだと思う。2次元の世界から3次元の世界へ、ベッドから屋内へそして屋外へ、生活空間を広げ、今ここに生きているということを感じ、天の恵みの中で、家族の愛の中で、多くのチームの協働の中でその瞬間まで実存を感じ、ゆっくりした時間の中でいのちを見つめ合う事ができていくのである。在宅ケアは人間らしく生きるということの最も大切な希望につながる支援だと思う。
老いるということは、すべての人がかならず歩む道であり、自らの死から目をそらさず、日頃から自分の人生の最終章を如何に過ごし終えていくかを考えることはとても大切だと思う。ある患者さんは「死は人生の終末ではない。生涯の完成である」と言われている。単身高齢者も増加し、自宅で最期を迎える事ができない場合にも、ホームや施設で最期までその人の尊厳を持って人生を締めくくっていけるようなホスピスを目指していく必要があると思う。
和解と懺悔
和解と懺悔
「身体的に辛い中で、自分の良いところに目を向けて、前を向いていきましょう」とベッドサイドでお話しすると、彼から
「光の見えない者に、何が出来るか」と強い調子で言葉が戻ってきた。
廊下にでて
ああ、そうか。光が見えないとは生きる希望が持てないということなのだ。生きる希望が持てないのに前を向くことも、そのような気持ちにもなれないといわれている。私の言葉が如何に空虚に感じられたことかと思い、廊下を歩きながら、自らの言葉の罪深さを思い、私の言葉が頭の中をぐるぐると回り続けた。私はじくじたる思いに駆られた。
彼はまだ50歳代であった。がんを患い、他の医療機関で治療を受け続けてきたが、呼吸も苦しくなり、言葉を発するのも次第に難しくなっていた。すべてが受け入れられず、すべてを拒否され、ベッドに臥床し、カーテンを閉め、食事も摂らず、終日起きることもなく、看護師のケアも受け入れないという状態であった。自暴自棄的ですべてを拒否するというものであった。
私がベッドサイドに診察に向かっても、会話は成立せず、背を向け布団をかぶったままであった。お姉さんが傍にいたが、私にすまなさそうな表情を浮かべていた。
数日後、夕方ベッドサイドに行くと、別れた奥さんが来ていた。彼と奥さんとの会話はその場に居合わせないので知る由もなかった。しかし、その日を境に彼の表情、行動に変化が見られ始めた。
奥さんの押す車椅子に乗って、自室から廊下に出はじめた。デールームから花の咲いているベランダにでて、外の景色を眺め、山の彼方を静かに眺めていた。山並みの彼方には自分の生活している村がある。大きく深呼吸をした。青空にはぽっかり白い雲が浮かんでいた。奥さんと言葉を交わす姿がみえた。ベランダから眺めている彼の後ろ背に奥さんが静かに語りかけていた。
彼は孤独で寂しかったのである。
彼は家庭内暴力で奥さんも離婚し、娘も離れていっていたのである。自分が自らまねいた結果であった。
自らが病の床に伏し、次第に自らの置かれた病状の変化に気づき、相談する者もなく、こころの辛さに寄り添ってくれる者は姉さん以外誰もいなかった。
そのような時、最初の言葉がほとばしり出たのである。
「光のみえない者に何が出来るか」
彼は寂しく、切なく、自らの死と向き合い、すべてのことが受け入れられなかったのである。
その時、別れた奥さんが彼のもとにある日の夕方来たのである。多分姉さんが奥さんに連絡したのであろう。
その時の彼と奥さんの会話は知る由もないが、彼の変化で理解することが出来た。
たぶん彼は奥さんに
「ごめん。悪かった。俺を許してくれ。苦労をかけてすまなかった。娘にも父として何もしてやらず、本当にすまなかった。許してくれ」
彼のこころからの懺悔の言葉が迸り出たのではないか。
奥さんがそれを許してあげられたのでしょう。
彼の長年月の積もり積もった心の重荷が少しずつ緩んできたのであろう。彼の病床での変化が起こってきた。全く拒絶していた食事にも少しずつ向かい、奥さんの押す車椅子で自分の部屋から外に出るまでに心が変化してきたのである。
人間は自分の人生を歩む。縁の中で自分の人生を歩むのである。自分がどんな人生を歩もうとも、自分の選択で、決断で行動しているのである。一期一会の中で自らが何を掴み、何を行い、何を幸せと感じるかは、ひとえに己の心のなかにあるのである。泣くも、笑うも,悦ぶも、悩むも心一つなのである。自らの因縁によって目の前の結果があり、自我に固執すれば畢竟苦の中にあるが、それを苦と感じるか、幸せと感じるかは心一つなのである。
多くの患者・家族との出会いから、多くのことを学ばせていただいている。その中で、生死の世界に直面した時、一生懸命生きてきた人生に意味があり、納得して、後に託し、安寧な心になれるかがとても大切であると感じる。過去を背負い、今を生き、現世の肩の重荷を下ろして、永劫の未来へ向かって歩んでいただきたいとつくづく思う。私は「燈明を照らす」ことが大切と思っている。多くの苦悩ある人々の足元にそっと明かりを照らすことができ、ひとり一人が自らの生死の世界から目を離さず、自らが諦観され、心穏やかになっていただきたいと祈るばかりである。ひとえに自らの心のあり方と思われる。
彼は数週間、奥様やお姉さんの支えの中で過ごされていた。次第に身体的な限りがみえてきた時、
「もういいよ。本当に皆にお世話になった。もう思い残すことはない。身体も本当に辛くなったので、そっと旅立って行きたい。よろしく頼むよ」と私にかすれる声で言った。
彼のこの世の生きてきた人生の中で、最期に肩の重い荷物を下ろすことができ、心穏やかに旅立っていかれたと思えてならない。奥様のおかげである。奥様も彼の最期の懺悔に心の中に明かりが灯ったことだろう。
祈り
祈り
我が国におけるspiritualの意味すること
皆さんはspiritual pain、spiritual careなどの言葉を聞かれたことがあるだろうか。
元東北大学医学部麻酔・救急医学講座疼痛制御科学分野教授で現在八戸看護専門学校校長の山室誠先生から我国におけるspiritualへの概念について私に意見を求められた。先生は医療におけるspiritual pain、spiritual care等について書簡をくださった。
その中で
2012年、春の高校野球の開会式での石巻工業高校、阿部翔人(しょうと)君の選手宣誓は、被災者が苦しんでいるのはspiritual painであることを全身全霊で受け止めているものであった。
チームのメンバーの中にも身内を亡くした人、家が流された選手も居たが、そんな彼らが、支援活動にいそしみながら作り上げた宣誓文でした。
「被災された方の中には、苦しくて心の整理が付かず、今も当時のことや、亡くなられた方が忘れられず、悲しみに暮れている方がたくさん居ます。人は誰でも、答えのない悲しみを受け入れることは苦しくて辛いことです」
彼ら自身は、Spiritual Painなどという言葉を知らなかったと思うが、この宣誓文に勝るSpiritual Painの説明はないと思ったと述べられている。
私たちが日常生活の中で病気もせず、家庭も円満で、自分の仕事に邁進して身体的にも精神的にも社会的にも落ち着いているときにはあまり深く考えることもない。このような生活の中で破れが生じた時、例えば病気になり、生死の世界に直面した時、会社が倒産して自分の日々の生活を真剣に考えなければいけなくなった時、心が病み日々の生活がこなせなくなってきた時、
どうして、自分が「がん」になったのだろう?
他人ではなく、何故、私が被災者になったのだろう?
何もかも失ってしまった今から生きて行く価値があるのだろうか?
どうして私ではなく、あの人が死んでしまったのだろう?
なぜ私がいじめられなければいけないのか?
というような思いが頭をもたげてくる。
これがspiritual painと言われるものである。「不条理で答えのない自らへの問いに、苦しみながらも何とか人間として生きていくための存在能力に関わる事柄」だと考えられる。
日本のホスピス関連の第1人者である、金城学院学院長の柏木哲夫先生は、精神科医として、「苦痛や苦難が“心の病”で留まっている間は“欝”の対応でよいが、“魂”の病気になると“自殺念慮”が出てくるように思うと言われた。
山室先生は書簡の中で次のように述べている。また「Spiritual Pain」が、“死に至る病のTotal Painの構成因子”であることから考えて、spiritual painとは
「希死願望を起こさせるような苦痛と苦難」と考えられる。さらに希死願望とは、生きる価値と生きる意味と生きる目的を失った場合に生じると言われる。
がん終末期患者の「死ぬのが怖い」「死にたくない」と言うのも、逆説的な表現で、広い意味での希死願望に入るそうである。
したがってSpiritual Careとは、希死願望を喪失させるためのCare、すなわち生きる価値と生きる意味と生きる目的を実感して「こんなに苦しい“にも関わらず”、今は生きて行く望みも見当たらない“にも関わらず”生きる、生きて行こう」と言う想いを起こさせるような支援や対応と言うことになる。
そして、これらの支援や対応を「Spiritual Care」と言い、「Spiritual Care」により、「Spiritual Pain」が解消される事が「癒し」(Healing)になる。
医療の現場、特にホスピス緩和医療分野ではTotal Painという言葉が使われる。日本語では「全人格的疼痛」あるいは片仮名で「トータルペイン」と言われている。
近代ホスピスの母と言われるシシリー・ソンダース女史が提唱された概念であるが、Painと言う言葉は痛みに限定されず、「自分には重荷だ」とか「辛い」というような意味でも、It’s my Pain などと言うと述べている。苦痛としては身体的な痛み(physical pain)、精神的な痛み(mental pain)がある。さらに痛みと言うよりは苦難と捉えた方が理解しやすい社会的な痛み(social pain)がある。これは病気による失職とか借金による家計の破綻など経済的な苦難、家族が背負う労力的、時間的な負担など、社会的な問題から起こる苦しみを言う。4つ目がSpiritual Painである。この概念が紹介された当初は、宗教的な痛みとか魂の痛みなどと訳された事もあるが、緩和医療の分野では、「スピリチュアル」と、そのまま片仮名で表記することにした。たとえば、脳血管障害の患者は、我々の目に見えるのは麻痺という身体的な症状であっても、患者・家族は精神的、社会的、spiritualな苦痛と苦難があるはずである。
しかし、麻痺という身体的な症状が前面に大きく出ているので、医療従事者はそれ以外の痛みや苦しみに気付かないし、気付こうともしない。たとえ気付いたとしても、医療保険で治療される対象には考えない。まして、家族の苦しみや悩みなどは医療従事者には無関係なことでした。
「Mental Pain」の症状が前面に出ている患者は、強い症状しか見ない従来の医療の考え方から言うと、鬱・適応障害・認知症などの精神科担当の疾患と言うことになる。
しかし、Total Painの視点で見直すと、精神的疾患の患者も、不眠や食欲不振などの身体的症状に加えて、家計の破綻や誤解による人々の差別など社会的苦難、さらには自殺念慮などのspiritualな面での苦痛と苦難があるはずである。これらは精神科医による医療保険での治療の対象とはならなくとも、看護や介護などを含めた広い意味での医療の対象として考慮されなければ、本当の治療にはならないと言う考えである。
同様にSocial Painが強い人々は、従来の考え方からすれば社会的弱者と言われ、医療とは無関係のように取り扱われてきた。しかし路上生活者や落ちこぼれと言われる人々は、アルコール中毒や生活習慣病など身体的症状、そして働けない・栄養不足などの困窮状態から来る社会的苦難、さらに家族を見捨てた罪の意識など、精神的にもspiritualな面でも苦痛と苦難を背負っている。そこで単に経済的な援助のみならず、Total Painの中のSocial Painの要素が強い患者と認識した上での対応が必要となる。
ホスピスでのがん終末期医療を経てソンダース女史は、「がんに限らず、どんな病気の患者でも、その背景には必ず身体的、精神的、社会的、スピリチュアルの4つの苦痛と苦難がある。我々が病人あるいは患者と呼んでいる人々の身体的疾患とは、4つの要因の内、身体的苦痛の部分が大きいに過ぎない」。だから「Total Painを緩和するTotal Careこそ医療の本質である」として、これをホスピス運動(Hospice Movement)と命名し、1980年初めから普及活動を行っている。
本邦と異なり、欧米ではTotal Painの概念は、がんに限定されず、AIDZや神経難病などの対応systemとしても、その守備範囲を広げて来た。
しかし、それ以上に評価されるのは、医療従事者中心の医療や疾患の治癒だけを目指してきた医療の在り方自体の変革を目的とするホスピス運動(Hospice Movement)として成果を上げてきた事である。
Hospice Movementは、1991年9月にポルトガルのリスボンで開催された第34回世界医師会総会で採択された「患者の権利に関するリスボン宣言」や1995年の「パリ宣言」を生みだした。これらが、患者の決定権の尊重やinformed consentなどに繋がった。
そして、何と言っても決定的な事は1998年(平成10年)にWHOの健康の定義の改変を促した事である。
従来のWHOの健康の定義が制定されたのは、60年も前の1951年(昭和26年)の事だった。
この時点でも、既に、「健康とは身体的のみならず、精神的・社会的に健やかなる状態」と定義されていた。
1998年にWHO憲章の見直しの一環として健康の定義の変更が検討されることになった。
各国のspiritualに関する宗教的な見解の相違から、批准はまだだが、spiritualの他にも、健康とは流動的であるという意味でdynamicが付記された。
ここで理解してもらいたいのは、spiritualなものとは世界規模で各国を代表する人々が宗教や風俗の違い、言語の壁を乗り越え、わざわざ言葉の定義を決めてまで真剣に討議するような、それ程大切な事柄だと言う事である。
それにも関わらず、本邦ではspiritualについては出来るだけ触れないようにしている。
”がん”や“エイズ”など死に至る病の医療や看護からようやく学んだTotal Painの概念の根本を支えるspiritualという言葉の重みも深さも、畏敬の念も日本人にはないように感じるとのべている。
私はspiritual painとは実存の喪失の時に湧き上がる苦悩だと思っている。Spiritual Painを、魂の痛みあるいは霊的な痛みと考えればその苦悩を救うものは祈りしかにように思う。
在宅ホスピスのすすめ
在宅ホスピスのすすめ
私は2013年3月31日をもって、33年間奉職した綜合病院山口赤十字病院を定年退職する。元気でこれまで勤めることが出来、本当に多くの皆さんにお世話になった。
振り返ってみると、生まれ故郷の山口赤十字病院に就職したのは1979年10月であった。当時、私が生まれ育った仁保の自宅で、母が年老いて一人で生活していた。当時鳥取大学法医学教室にて将来は大学人として実務、研究、教育に携わるか、親の面倒を診るか悩んだ。私を含め5人の子どもを育ててくれた母が、人生最後に一人の生活はあまりにも申し訳ないと思い、当時の吉富院長先生にお話ししたところ、快く「親の面倒を見るなら、喜んで就職を許します。一所懸命に内科学を勉強せよ」とお許しをいただいた。当時の内科には藤本元副院長、為近前院長、昨年お亡くなりになった田中医院の田中先生、鴻城医院の渡邊先生らがおられ、多くの研修をさせていただき、幅広く内科学を学ばせていただいた。内科全般、特に消化器内科の研鑽を積ませていただいた。
1990年、私が診断した直腸がんの一人の患者さんとの出会いが、その後の私のホスピスへの道を拓いてくださったと思う。当時再発転移して次第に衰えて死がみえてきた彼が市民運動で「癌と末期医療を考える会」を立ち上げるにあたり、近代医学の発達と社会の中での病院死が如何に本人、家族にとって多くの苦悩の中でミゼラブルに人生を終えているかを指摘し、もっと人の死を大切にした医療現場を造って欲しいとの訴えに心動かされ、ホスピス緩和ケアをスタートした。1992年に県内で初めての緩和ケア病床をつくり、また、在宅訪問診療(ホスピスケア)をはじめた。当時は訪問看護も、看護ステーションも何も無い時代だった。その後、病院に訪問看護が出来、法律によって訪問看護ステーションが作られてきた。
1999年には全国の日赤で初めての25床の緩和ケア病棟を立ち上げ、今まで5000人近いがん患者、家族と係わり、4000人近い方々を病棟、在宅にて看取らせてもらった。その間、多くの患者さんから生きること、いのちの大切さを学び、これまで3冊の本(ひとひらの死、いのちの響〜ホスピスの春夏秋冬〜、ゆうにゆうにまあるくまあるく)を上梓することができた。
また、2003年全国で初めて行政を巻き込み山口市在宅緩和ケア推進事業に取り組み、年齢制限なく、がんの進行した方の自宅で福祉サービスが受けれるような体制を作ってきた。また、病院の皆様のおかげで、日本で最も伝統のあるホスピスの学会である日本死の臨床研究会の第29回全国大会を2005年に大会長として山口で開催することが出来た。病院の皆様の行動力の素晴らしさに改めて敬服したことを思い出す。
がん拠点病院の指定を受けるために、あるいは臨床研修病院指定を認めていただくために奔走したことを思い出す。一つ一つが自分の使命と考え邁進してきたと思う。振り返ってみると、何もなくとも実践して行動していけばレールは後からできるものだということを学んだ。
今後、自分のライフワークのホスピスを続けたいと考え、新たに4月より山口駅近くで「すえなが内科在宅診療所」を開設して、多くの患者さんの苦悩に寄り添い、在宅ホスピスケアを行なっていくこととした。
我が国では高齢社会の中で、女性の平均寿
命は86歳、男性は80歳となってきた。
しかし、入院医療や施設介護が中心であり、
国民の60%が自宅での療養を望んでいるにもかかわらず、我が家での看取りは12%と低下している。1977年に在宅死から病院死となり、現在は88%が病院死である。
私をホスピスの道に導いた彼は1990年にすでに「近代医学の発達と社会の中での病院死が如何に本人、家族にとって多くの苦悩の中でミゼラブルに人生を終えているか」を指摘していた。
死亡者数は2040年には今より40万人増加する。私のような団塊世代の最終章の人生の締めくくり方が問われているのである。
元気な間は自分で積極的に生き、社会に貢献し、尊厳を保ちながら暮らし続けることが出来るような社会の実現を目指し、高齢者が住み慣れた我が家や地域で自立した生活が出来る事が大切である。そして地域のコミュニティーの中の医療、看護、介護、福祉の連携の中で自分に納得した人生の最終章を生き抜いていくことが大切であると思う。
私たちは天命をいただき、自分の人生を生き抜き、老い、そして人生を締めくくっていかなければいけない。この世の存在は医療や人間の力のおよばない世界である。
いのちを看取るということは残される人、愛する家族、友人がその人と共に歩んだ全人生を看取ることである。看取られる人は苦しさから解放されるが、残される人はそれを乗り越えて生きて行かなければならない。ここに、いのちの連続性があると思う。
日々是好日
日々是好日
中国の禅僧雲門は「心において無事、事において無心なる人の生活は、杞憂を超えて毎日毎日が好日になる」と伝えていると禅聖典に載っている。すなわち良いことも悪いことも、取り巻く現実を徹底して見据えた上で、ここに今、実際に生きて在ることの感謝を知る。そうすれば毎日が好日である。
この言葉を私は記載する事が多い。ホスピスの現場において自らのこの世の存在、すなわち生死(しょうじ)の世界に直面した時に沸き起こってくる根源的な叫びに私たちに何が出来るかという事が問われているのである。ホスピスとは私たちひとり一人がいただいた天命をその瞬間までその人らしく生きるという事に尽きると思う。ホスピスの現場では患者と家族の苦悩を少しでも和らげ、自らのおかれている現実の辛さから目を背けず、自らの人生、いただいた「いのち」に向き合う事が出来る事がとても大切である。そのためには身体的な苦痛からの解放は必要条件にすぎない。ひとり一人が自らのおかれている「いのち」の終焉に肩の力を抜き、重荷を下ろして自らが生きてきた人生に意味を見いだし、納得し、後に託して、心穏やかに安寧な気持ちで今を過ごす事が出来るかが問われているのである。
緩和ケア、緩和医療ということが国の政策として広く認知されているが、その事は入り口の事にすぎないと思う。もっと深いところに私たちの役割があると考える。私たちのこの世の存在が無限の世界からいただいた「いのち」であり、唯一無二の存在であり、誰にも変われない存在であり、そのいただいた「いのち」にはひとり一人に使命があり、ここに存在している事に意味があるということに気づけるような関わりがとても大切である。その事に私たちが如何に寄り添い、ゆっくりした時間の中で架け橋が出来るかという事である。
私たちひとり一人に心の柔らかさがなければいけない。ホスピスの現場で私たちに心にゆとりがなければ、患者や家族への安心感は伝わらない。私はスタッフにいつも心はゴム毬でなければいけない、心は鏡では自らが疲れますよと伝えている。心のゆとりのあることがとても大切なのである。鏡であれば自らが疲れて、よい関わりが出来なくなると考える。
ホスピスの現場は患者・家族が安心して自らの生活の中で今を生きることがとても大切である。生活の中で苦しみがなく、いただいた「いのち」を終えていけるような時間と空間がとても大切である。その場は何処にもあるのである。患者や家族が選択するのは自らが住み慣れた我が家でも病院でも緩和ケア病棟でもいずれの場でもよいと思う。患者・家族が安心して過ごせることが大切なのである。選択は患者・家族にあるのである。私たちはそのシステムが出来るように連携を作っていかなければいけないのである。
ある年老いた母と二人暮らしの息子が不治の病にかかり、懸命に治療に専念するも、次第に病気が進行し、厳しくなってきた。本人は年老いた母に自分の今の状況を知らせたくないという親思う気持ちで、母に会わないできた。年老いた母は姪御さんが一生懸命に面倒をみてあげていた。
彼の病体が厳しくなった時、彼に
「お母さんに一目会ってあげては如何ですか。お母さんに心配をかけないようにという気持ちはよくわかりますが、もし、貴男が亡くなられて、初めて息子の死を知られることは大きな悲しみとなって、嘆かれると思いますよ。貴男も一目お母さんに会って、先に逝くことのつらい気持ちとお母さんへの感謝の気持ちを伝えてあげられと、お母さんの気持ちが少しは安らぐのではないでしょうか」
彼は黙って何も語らなかった。
姪御さんに病状が厳しいことを伝え、年老いた母を連れて来られるように勧めた。
母は息子の病気のことは何もわからない様子であった。母はしきりに息子との生活や家の話をしてくださったが、病状がきわめて厳しくもうすぐお別れになることを伝えた。耳が遠いので理解できない様子であった。息子の手をにぎり、早くよくなって帰って来いよと言われる。私を見つめ手を合わせ、祈るようにされる。彼は母に、もういいよというように自分の口元に指をあて、そっとしておいてという仕草をした。お二人の姿に涙無くして見つめることは出来なかった。そっと、見守ってあげることしか出来ないが、お二人のこころが繋がっていると思った。
吉田松蔭の「親思う心にまさる親心。
今日のおとづれなんと聞くらん」の辞世の句を思い出す。
お二人の悲しみが少しでも癒されることを祈るばかりである。
ホスピスではそれぞれの人生を歩まれた最期にその人の人生を肯定し、まるごと包み込んでくれる人がいることが大切だと思う。
大きな存在のなかのいのち
「大きな存在の中のいのち」
岡部医院を宮城県名取市で1997年開設した岡部健医師は、本格的に在宅緩和ケアを專門とする在宅支援診療所として我国でも草分け的に在宅医療を実践してきた。彼は「緩和ケアは、医療における最終目的の大きな転換であると考えている。緩和ケアの目的は、個々の患者様の残された時間のQOL(生活の質)を最大限に向上させることではないか?緩和ケアは医療だけではなく福祉的側面との複合体である。現状の緩和ケアはホスピス病棟、緩和ケア病棟、病院の中で医師と看護師で行われているが、在宅の中では介護との連携は必須である。QOL評価を軸として、医療と介護の有機的結合をはからなければならないと思う。在宅での死の看取りから看取りの機能を医療者から一般社会に戻し、その中から生まれたタナトロジー(死生学)の形成も重要と考えている」と述べている。1999年には医療グル−プ爽秋会を設立し、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、訪問看護事業所などを併設し、医師、訪問看護師、ケアマネージャー、ヘルパー、薬剤師、作業療法士、ボランティア、チャプレンなどが有機的に関わり、住み慣れた我が家での患者・家族に寄り添う医療、看護、福祉、介護を提供してきた。
その彼が2010に進行胃がんが見つかり、治療を受けながら医療も行ってきた。次第に体力の衰えを感じ始めた2012年6月に彼が私と話がしたいという希望があるという連絡が私のもとに入った。彼とは日本死の臨床研究会や日本ホスピス緩和ケア協会、あるいは講演会などでホスピスや在宅ホスピスケア、死生観などについてこれまでも語る機会はあった。
2012年7月1日に仙台市の彼の自宅を訪れた。
癌性腹膜炎がすすみ、食事がなかなか進まず,痩せが目立っていた彼が玄関まで迎えに出てくれた。応接間のソファーになりながら彼が自分の死生観や我国のホスピスのあり方などを伝えてくれた。彼の語ることばは深い洞察力と日本文化、宗教、医療への幅広い知識が溢れでてきた。その知識の深さに敬服するばかりであった。
医療と医学について医療は、医学と言う科学の限界点を承知した上で行うべき事が必要である。根拠に基づいた医療(Evidence-based medicine、EBM)で悪い事は、観察対象になっていない事象は、存在しない事になってしまう事である。例えば自分が今排便がスムーズにあることがとてもありがたいと感じるが、EBMで排便あり、排便なし、の二つでは、自然排便とはなんと素晴らしい事なんだろうと言う岡部の気持は、存在しない事として、消えてしまう。また、我国では外国のガイドラインや教科書を持ってきて、それを当てはめようとする傾向にある。薬物療法は、世界共通だが、それ以外(緩和医療の項目)はすべて各国で異なっている。介護福祉関係は、法律が異なるし、死生観については文化が異なる。外国のやり方や方法が、日本にそのまま当てはまるわけがない。日本の緩和医療の源流は結核療養所にあると思われるので、そこに求めるのが良く、外国のホスピスに求めるのは間違いではなかろうか。結核の場合は、病名や病状が徹底して伝えられていたから、患者は病気についても、死ぬ事も含めて知っていた。しかし,がんの患者に真実を知らせなかったので(患者が病気について何も知らなかったという点で)、がん治療から始まった日本の緩和医療のあり方は結核療養所とは大きく異なると考えられる。
人間の生き方や人間生活と自然との調和(ecology)まで含むホスピス運動を、医療という狭い世界に閉じ込めたのが、本邦の緩和医療である。そこに間違いがある。
死の方から生き方を見るのは間違いである。生死に関する事柄は、今日を生きるという視点から、結果としてあちらに逝くがん患者の治療やケアを見直すべきである。お葬式の方法や看取りの方法も世界中で、その国により、その地方により、全く別々なのだから、「死」の方から「生」を見れば、バラバラになってしまう。むしろ、人が「生きる」と言う視点から、死を「生死の繋がり、あるいは生の連続帰着点」と考えて対応した方が良い。
人間も自然に生きる地球上にある生物の一つとして、人間を超える大きなものによって、あらかじめ遺伝子に組み込まれている現象の一つとして「お迎え」も「お知らせ」現象も在る、と考えるのが最も素直で、説明が付く考え方だと思われる。お知らせとは遠くの身内に、夢や予兆など何らかの形で現れて自らの死を知らせるような現象をいう。たとえば親父が夢枕に立ったので、急いで帰省したら亡くなったというようなことである・
また、この度の震災の亘理町の荒浜(あらはま)の被災地に立った時に感じたのは、「合理的にものを考えられる場所も、空間も、時間もない、まるで空襲で爆撃を受けた様な状況」だった。
そこに自分の身を曝したら、「ああ、人間と言うのは大きな存在にぶら下がって生きているんだな。個人が集合すると人間になるんじゃないんだ。実は逆なんじゃないか」と思った。この想いは、考えて、得たものではない。ふっと湧いてきた。「あそうか!」と体にストンと落ちてきた。あの場では、物を考えるはずの自我そのものが破綻していた。破綻した時に何が人間の心を支えられたのか、と言ったら、人間とは大きな命に繋がっているもんなんだ。俺が死ぬなんて事は、本当にちっぽけな事なんだ、という様な事が、リアルな感覚として自らの中から湧き出てきた。
これは非常に不思議な感覚だが、被災地に立った多くの人の共通体験でもある。これは集合的無意識論と言うべき現象だと考える。
自分がこのような病気になり、死と対峙する時、人間、病気になって弱ってくると意識が変わる。まず欲求がなくなって、どんどん悪くなるにしたがって植物化する。
体重が強烈に落ちて行く時に、だんだん欲求がなくなって行って、苦痛は無く、生きていたいと言う欲求もなく、いわゆる涅槃に行っちゃう、恐怖も、不安もない。(震災の時に感じた、自分はその一部であると言う)大きな生命体と一緒になっちゃうと言う感覚に近い。死んでいく前に苦痛や恐怖がないというプログラムが人間に組み込まれているとすれば、これは、次の世代に伝達する事はできない(後天的な獲得形質として子孫に伝えることは出来ない)。なぜ、人間に死んでいく前に苦痛や恐怖がないというプログラムがsettingされているんだろう、というと、そこで神様を感じた。
彼は自分の死を前にして感じる事を静かな口調で語りかける。そのことば一つ一つが重く、考えさせられる。
死の臨床における真のホスピスケアを求めて
死の臨床における真のホスピスケアを求めて
私は現在日本死の臨床研究会の顧問をつとめている。日本死の臨床研究会は1977年にスタートした我が国におけるホスピス緩和ケアの最も歴史ある研究会である。その原点は「死の臨床において、患者や家族に対する真の援助の道を全人的立場より研究していくこと」という会の目的にある。2011年度から世話人代表を引き継ぐことになった。
この研究会は約2600名の会員がいる研究会である。年に一度全国大会を行い、北海道から九州まで各ブッロクで支部大会が開催されている。医療関係者だけでなく一般の市民の参加型の研究会であり、学会にしない理由は市民に開けた立ち位置をとり、ひとり一人の「いのち」への向き合いを探求していく学問的研究会を目的としているからである。 医師、看護師、薬剤師、介護福祉士、医療ソーシャルワーカー、僧侶、ボランティア、一般市民など多岐にわたる職種からなる研究会である。
「死の臨床」とは死に直面した時、沸き上がってくる根源的な叫び、すなわち自分のこの世の存在が失われていくという苦悩、言い換えれば不条理な人生を直視したときの深いスピリチュアルぺインの中にある人々への寄り添いだと思う。
スピリチュアルペインとは己の実存の喪失と考える。私たちが生きていく上で最も大切なことは、あるいは生き甲斐とは自分の実存即ちこの世の存在の意味を感じ、生かされている、必要とされていると感じることであると考える。この実存の喪失、生きている意味の喪失こそがスピリチュアルペインだと考える。
ホスピスとは目の前に悩める人にいかに手をさしのべるかという哲学であり、私たち一人ひとりがいただいた「いのち」をその人らしく生ききることであり、医療をはるかに超えた「いのち」の尊厳を大切にすることだと考えている。
すべての人々はその苦悩の中で、その瞬間まで今を生きている。私たちがその専門性を生かし、チームとして患者・家族の皆様の心の架け橋や燈明を照らすことができるかが問われているのだと思う。死の臨床においてすべての人々が自分の人生に意味を見出し、価値を見出して安寧な気持ちで終えていけるようにありたいものである。
私たち一人ひとりは無限の世界からこの世に生を受け、人生を歩み、また無限の世界に戻らざるを得ない。どのような人生を歩もうとも、一人ひとりの人生には必ずキラリと光るものがあり、存在することそのことに意味がある。この二度とない人生をその瞬間まで実存を感じられるような場がとても大切だと思う。ホスピスの場とは悪くて、だめだから行く最期の場ではなく、その瞬間までより良く生きる場であり、それを支え、橋渡しをする場である。そのために、時間と空間がとても大切な場であり、いのちを通じて生きるということを考え、学ぶ場だと思う。病院でもホスピス緩和ケア病棟でも住み慣れた我が家でも患者さんとそのご家族が安心して最期まで過ごせることが大切なのだと思う。
そして、看取りとはその人が歩んだ全人生を看取ることであり、その看取りが出来るのは共に歩んだ家族や親族や友人などだと思いう。最期のいのちは家族にお返ししなければいけない。第35回死の臨床研究会の大会長の蘆野・長澤両会長がご挨拶の中で「学びの場である看取りを、非日常性の医療の場から日常の生活の場、あるいは日常的な環境になるように配慮した場に移すこと、医療者ではなく家族や親族あるいは友人などが看取るように配慮すること、地域社会が看取りを支援することが、今重要であると考えます」と言われている。この研究会の原点だと思う。
がん対策基本法に基づき、国民に広く緩和ケアの普及・啓発がなされ、医療的な面では進歩し続けている。しかし、金城学院大学学長の柏木先生のいわれる人の死は医学的出来事ではなく、人間学的出来事であり、社会学的出来事であるということである。
医療の進歩に伴い多くの恩恵がもたらされているが、人の死は決して医療では救えない。この世の存在は医療とか人間の力では及ばないことに気づかなければいけない。現代医療のアンチテーゼとして死の臨床研究会が産声を上げた原点を噛み締めなければいけないと考える。
今後、我が国を取り巻く環境はますます複雑化してきている。少子高齢化の中で、多死社会の中で一人ひとりの人生の生き方や終え方の価値観も変化し、多様化してくる。
医療、看護、介護、福祉の現場で、一人ひとりのいのちを大切にする智恵と工夫がますます重要になってくる。日本死の臨床研究会がなすべき役割は現場の実践を生かし、実践活動の学びの場となり、広い視野にたって益々発展していく事が大切であると考える。
死とは忌み嫌うものではなく、人生をやり終えた、あるいは自分の人生に納得し、後に託し、安寧な気持ちで終えていくという温かいものでなければいけないと考える。そんな生き方がとても大切だと思う。
今日も病棟で若い30代の若者が意識無く、ケアを受けている。その奥様と二人の小さな子どもたちがそばで過ごされ、普通の生活の営みがなされている。子どもは幼稚園にも病室から通っている。ここが家なのである。そこにはいのちの息吹が感じられる。いのちがとても愛おしく、ここに存在することに意味があるのである。私たちは今、ここに存在していることがすばらしいことに気づかなければいけない。
緩和ケアの取り組みとホスピスのこころ
緩和ケアの取り組みとホスピスのこころ
山口県のホスピス緩和ケアの歴史は1990年「がんと末期医療を考える会」が発足し、主宰の岡博氏が自らのがんの闘病を通じて「末期医療の充実とは何か。一言で言って人間の死を尊重してくれるということだ。現在、病院でいったい何人の人々がよく生き得、良く死に得ているでしょうか。懸命に生きてきた人生の場所が昭和二十三年の基準によるわずか二、六畳というベッド空間。プライバシーは全く認められず、他の患者の鼾やおなら、時には糞尿の臭い、同室者との人間関係を保つための妥協や追従。なに一つ思うようにならず、家族は肩身狭く付き添う病院の大部屋であるとは!」との訴えに触発され、私たちが院内に「ターミナルケア研究会」を設立したのがスタートです。1992年には県内で初めての3床の緩和ケア病床を設置し、本格的に取り組み始めました。その後、東病棟の建設に伴い、最上階に25床の承認施設としての緩和ケア病棟を1999年11月にスタートすることができました。日本赤十字社93病院の中で初めての緩和ケア病棟でした。開設記念講演に柏木哲夫先生に来ていただき、10周年開設記念に再び柏木先生にお出でいただくことができ、本当に嬉しく思います。1992年の緩和ケア病床をスタートした時点から我が家で最期を過ごしたいという患者の希望に添って、在宅ホスピスケアも行ってきました。患者さんやご家族が安心して過ごせる療養の場を提供するべき、入院,在宅,外来を三位一体としてシステム化することが大切であると考えて行動してきました。その結果、全国に先駆け山口市の行政の力を借りて2003年に山口市在宅緩和ケア推進事業を開始し、年齢制限なく1割の自己負担で福祉サービスが受けられる体制を造ってきました。その後、2004年山口市在宅緩和ケア支援センター開始。笹川医学医療研究財団ホスピスナース研修施設となり、2007年には日本医療機能評価機構付加機能評価緩和ケア機能認定を受けました。また、山口県在宅緩和ケア対策推進事業開始に伴い、山口県在宅緩和ケア支援センターを設置、2008年院内緩和ケアチームを開始しました。
このような歴史を振り返ってみて、何も無いところからスタートして苦節20年、感慨無量です。振り返ってみるに軌跡はあとから出来て来ることをつくづく感じます。いつも物事は成就出来るという信念のもとで歩み続けてまいりました。
今一番心配しておりますことはホスピスが次第に医療化していく我が国の現状をかんがみ、今一度ホスピスの意味を問い直さなければいけないと痛感しています。
ホスピス・緩和ケア病棟がスタートしたのは現代の病院死の中での人の死の尊厳があまりにもおろそかにされてきた経緯の中で、あるいは人の死の医学化の中で、身体的な生命のみに重きをおき、「いのち」としてのトータルケアを失ったことへのアンチテーゼとしてスタートしているのです。
良く考えてみるに私たちは天命をいただいているのです。すべての医療行為は延命のために行われ、天命を全うするためになされているのです。しかし、私たちがいただいたこの世の存在は医療や人間の力のおよばない世界であることに気づかなければいけません。
ホスピスの本質は目の前に悩める人にいかに手をさしのべるかという哲学であり、私たち一人一人がいただいた「いのち」をその人らしく生ききることであり、医療をはるかに超えた「いのち」の尊厳を大切にすることです。「死を看取る」ことは「生きること」を学ぶことであり、無限な世界からいただいたこの世の有限な「いのち」がふたたび無限の世界へ還って行くことへの場の提供です。人間存在における苦悩は生死(しょうじ)の世界に直面して沸き上がってくる根源的な叫びにたいして、内なる世界すなわち自分の生きてきた人生に意味、価値があることに気づき、その瞬間まで生きていることの喜びを感じるとともに、絶対世界すなわち大いなる力にゆだね、安寧な気持ちでこの世を終えていけるような架け橋の場がホスピスなのです。身体症状緩和は必要条件であり、ライセンスを持つ医療従事者は義務なのです。しかし、ホスピスの求められているのは生死(しょうじ)の世界への対応であり、悩める人に燈明(とうみょう)を照らすことであると思います。そのためにも医療従事者は自らの死生観,人生観などをしっかり築いていかなければいけないと考えます。
ホスピス・緩和ケアのこころ
ホスピス・緩和ケアのこころ
多くの人びとが生命を脅かす疾患に直面したとき、患者さんもご家族も同じ苦しみに見舞われます。特にがんと診断されたときから、患者さんもご家族も心はゆらぎの連続です。がんの進行や再発の不安を抱えながら、希望を見いだしたいと思いながら、日々の療養を続けておられます。身体的な苦しみがあると希望は見いだされなくなります。また、ご家族のこと経済的なことにも思い悩まれます。ご家族もその苦しみは同じなのです。治ってほしい、元気でいてほしいと願い続けられます。そして、スピリチュアル、魂のさけびがいつも不安となって頭をもたげてきます。いつまで生きられるのだろうかという将来への希望が見いだせなくなり、愛する家族や人生をともに歩んだ人と別れなければならないという不安、そして自分で自分のことができなくなり、この世にいただいた「いのちの存在」そのものに向きあわざるをえなくなります。その時私たちは何ができるのでしょうか。悩まれ苦しみにある患者さんやご家族の方の足下にそっと灯りをかざすことではないでしょうか。温かい心の通い合いであり、患者さんとご家族の不安に寄り添い、薄明るい歩むべき道筋が見えてくるように傍らに立つことではないでしょうか。ホスピスは悪くて、だめだから行く最後の場ではなく、その瞬間までより良く生きる場であり、患者さんとご家族を支え、橋渡しをする場であると思います。辛さを受け入れていくことはとても時間がかかります。一つ一つの希望が少しずつ削ぎ落とされていきます。これを自分で受け止めて行くにはとても時間がかかります。受け入れられなく、諦めになっていくことも多くあります。患者さんの苦しみに寄り添われるご家族には共に過ごす時間と空間がとても大切な場になるのです。ご家族の悲嘆が大きくならないように患者さんとご家族のこころの架け橋がとても大切だと思います。そして、ホスピスの場は患者さんがその瞬間まで生ききられ、寄り添われる家族はそのいのちを通じて生きるということを考え、乗り越えて、いただいた自らのいのちを生きるということを学ばれる場だと思います。そして、患者さんやご家族が辛いときに辛いと言え、孤独にしないように寄り添って行くことが問われていると思います。その瞬間まで自分のいただいた人生に意味を見いだされ、納得できるように、また安心して後に託すことができるような寄り添いと架け橋を大切にした、そのようなホスピスでありたいと思います。
在宅の良さは医療目線にならない、生活の中での存在であり、管理からの脱却であると考えます。多くのチームの協働により、患者・家族に寄り添い、生きる希望を見出し、その瞬間まで自立を支援し、皆様の尊厳性を大切にした関わりだと思います。2次元の世界から3次元の世界へ、ベッドから屋内へそして屋外へ、生活空間を広げ、今ここに生きているということを感じ、天の恵みの中で、家族の愛の中で、多くのチームの協働の中でその瞬間まで実存を感じ、ゆっくりした時間の中でいのちを見つめ合う事ができていくのです。在宅ケアは人間らしく生きるということの最も大切な希望につながる支援だと思います。
院長 コラム
和解と懺悔
和解と懺悔
「身体的に辛い中で、自分の良いところに目を向けて、前を向いていきましょう」とベッドサイドでお話しすると、彼から
「光の見えない者に、何が出来るか」と強い調子で言葉が戻ってきた。
廊下にでて
ああ、そうか。光が見えないとは生きる希望が持てないということなのだ。生きる希望が持てないのに前を向くことも、そのような気持ちにもなれないといわれている。私の言葉が如何に空虚に感じられたことかと思い、廊下を歩きながら、自らの言葉の罪深さを思い、私の言葉が頭の中をぐるぐると回り続けた。私はじくじたる思いに駆られた。
彼はまだ50歳代であった。がんを患い、他の医療機関で治療を受け続けてきたが、呼吸も苦しくなり、言葉を発するのも次第に難しくなっていた。すべてが受け入れられず、すべてを拒否され、ベッドに臥床し、カーテンを閉め、食事も摂らず、終日起きることもなく、看護師のケアも受け入れないという状態であった。自暴自棄的ですべてを拒否するというものであった。
私がベッドサイドに診察に向かっても、会話は成立せず、背を向け布団をかぶったままであった。お姉さんが傍にいたが、私にすまなさそうな表情を浮かべていた。
数日後、夕方ベッドサイドに行くと、別れた奥さんが来ていた。彼と奥さんとの会話はその場に居合わせないので知る由もなかった。しかし、その日を境に彼の表情、行動に変化が見られ始めた。
奥さんの押す車椅子に乗って、自室から廊下に出はじめた。デールームから花の咲いているベランダにでて、外の景色を眺め、山の彼方を静かに眺めていた。山並みの彼方には自分の生活している村がある。大きく深呼吸をした。青空にはぽっかり白い雲が浮かんでいた。奥さんと言葉を交わす姿がみえた。ベランダから眺めている彼の後ろ背に奥さんが静かに語りかけていた。
彼は孤独で寂しかったのである。
彼は家庭内暴力で奥さんも離婚し、娘も離れていっていたのである。自分が自らまねいた結果であった。
自らが病の床に伏し、次第に自らの置かれた病状の変化に気づき、相談する者もなく、こころの辛さに寄り添ってくれる者は姉さん以外誰もいなかった。
そのような時、最初の言葉がほとばしり出たのである。
「光のみえない者に何が出来るか」
彼は寂しく、切なく、自らの死と向き合い、すべてのことが受け入れられなかったのである。
その時、別れた奥さんが彼のもとにある日の夕方来たのである。多分姉さんが奥さんに連絡したのであろう。
その時の彼と奥さんの会話は知る由もないが、彼の変化で理解することが出来た。
たぶん彼は奥さんに
「ごめん。悪かった。俺を許してくれ。苦労をかけてすまなかった。娘にも父として何もしてやらず、本当にすまなかった。許してくれ」
彼のこころからの懺悔の言葉が迸り出たのではないか。
奥さんがそれを許してあげられたのでしょう。
彼の長年月の積もり積もった心の重荷が少しずつ緩んできたのであろう。彼の病床での変化が起こってきた。全く拒絶していた食事にも少しずつ向かい、奥さんの押す車椅子で自分の部屋から外に出るまでに心が変化してきたのである。
人間は自分の人生を歩む。縁の中で自分の人生を歩むのである。自分がどんな人生を歩もうとも、自分の選択で、決断で行動しているのである。一期一会の中で自らが何を掴み、何を行い、何を幸せと感じるかは、ひとえに己の心のなかにあるのである。泣くも、笑うも,悦ぶも、悩むも心一つなのである。自らの因縁によって目の前の結果があり、自我に固執すれば畢竟苦の中にあるが、それを苦と感じるか、幸せと感じるかは心一つなのである。
多くの患者・家族との出会いから、多くのことを学ばせていただいている。その中で、生死の世界に直面した時、一生懸命生きてきた人生に意味があり、納得して、後に託し、安寧な心になれるかがとても大切であると感じる。過去を背負い、今を生き、現世の肩の重荷を下ろして、永劫の未来へ向かって歩んでいただきたいとつくづく思う。私は「燈明を照らす」ことが大切と思っている。多くの苦悩ある人々の足元にそっと明かりを照らすことができ、ひとり一人が自らの生死の世界から目を離さず、自らが諦観され、心穏やかになっていただきたいと祈るばかりである。ひとえに自らの心のあり方と思われる。
彼は数週間、奥様やお姉さんの支えの中で過ごされていた。次第に身体的な限りがみえてきた時、
「もういいよ。本当に皆にお世話になった。もう思い残すことはない。身体も本当に辛くなったので、そっと旅立って行きたい。よろしく頼むよ」と私にかすれる声で言った。
彼のこの世の生きてきた人生の中で、最期に肩の重い荷物を下ろすことができ、心穏やかに旅立っていかれたと思えてならない。奥様のおかげである。奥様も彼の最期の懺悔に心の中に明かりが灯ったことだろう。
祈り
祈り
我が国におけるspiritualの意味すること
皆さんはspiritual pain、spiritual careなどの言葉を聞かれたことがあるだろうか。
元東北大学医学部麻酔・救急医学講座疼痛制御科学分野教授で現在八戸看護専門学校校長の山室誠先生から我国におけるspiritualへの概念について私に意見を求められた。先生は医療におけるspiritual pain、spiritual care等について書簡をくださった。
その中で
2012年、春の高校野球の開会式での石巻工業高校、阿部翔人(しょうと)君の選手宣誓は、被災者が苦しんでいるのはspiritual painであることを全身全霊で受け止めているものであった。
チームのメンバーの中にも身内を亡くした人、家が流された選手も居たが、そんな彼らが、支援活動にいそしみながら作り上げた宣誓文でした。
「被災された方の中には、苦しくて心の整理が付かず、今も当時のことや、亡くなられた方が忘れられず、悲しみに暮れている方がたくさん居ます。人は誰でも、答えのない悲しみを受け入れることは苦しくて辛いことです」
彼ら自身は、Spiritual Painなどという言葉を知らなかったと思うが、この宣誓文に勝るSpiritual Painの説明はないと思ったと述べられている。
私たちが日常生活の中で病気もせず、家庭も円満で、自分の仕事に邁進して身体的にも精神的にも社会的にも落ち着いているときにはあまり深く考えることもない。このような生活の中で破れが生じた時、例えば病気になり、生死の世界に直面した時、会社が倒産して自分の日々の生活を真剣に考えなければいけなくなった時、心が病み日々の生活がこなせなくなってきた時、
どうして、自分が「がん」になったのだろう?
他人ではなく、何故、私が被災者になったのだろう?
何もかも失ってしまった今から生きて行く価値があるのだろうか?
どうして私ではなく、あの人が死んでしまったのだろう?
なぜ私がいじめられなければいけないのか?
というような思いが頭をもたげてくる。
これがspiritual painと言われるものである。「不条理で答えのない自らへの問いに、苦しみながらも何とか人間として生きていくための存在能力に関わる事柄」だと考えられる。
日本のホスピス関連の第1人者である、金城学院学院長の柏木哲夫先生は、精神科医として、「苦痛や苦難が“心の病”で留まっている間は“欝”の対応でよいが、“魂”の病気になると“自殺念慮”が出てくるように思うと言われた。
山室先生は書簡の中で次のように述べている。また「Spiritual Pain」が、“死に至る病のTotal Painの構成因子”であることから考えて、spiritual painとは
「希死願望を起こさせるような苦痛と苦難」と考えられる。さらに希死願望とは、生きる価値と生きる意味と生きる目的を失った場合に生じると言われる。
がん終末期患者の「死ぬのが怖い」「死にたくない」と言うのも、逆説的な表現で、広い意味での希死願望に入るそうである。
したがってSpiritual Careとは、希死願望を喪失させるためのCare、すなわち生きる価値と生きる意味と生きる目的を実感して「こんなに苦しい“にも関わらず”、今は生きて行く望みも見当たらない“にも関わらず”生きる、生きて行こう」と言う想いを起こさせるような支援や対応と言うことになる。
そして、これらの支援や対応を「Spiritual Care」と言い、「Spiritual Care」により、「Spiritual Pain」が解消される事が「癒し」(Healing)になる。
医療の現場、特にホスピス緩和医療分野ではTotal Painという言葉が使われる。日本語では「全人格的疼痛」あるいは片仮名で「トータルペイン」と言われている。
近代ホスピスの母と言われるシシリー・ソンダース女史が提唱された概念であるが、Painと言う言葉は痛みに限定されず、「自分には重荷だ」とか「辛い」というような意味でも、It’s my Pain などと言うと述べている。苦痛としては身体的な痛み(physical pain)、精神的な痛み(mental pain)がある。さらに痛みと言うよりは苦難と捉えた方が理解しやすい社会的な痛み(social pain)がある。これは病気による失職とか借金による家計の破綻など経済的な苦難、家族が背負う労力的、時間的な負担など、社会的な問題から起こる苦しみを言う。4つ目がSpiritual Painである。この概念が紹介された当初は、宗教的な痛みとか魂の痛みなどと訳された事もあるが、緩和医療の分野では、「スピリチュアル」と、そのまま片仮名で表記することにした。たとえば、脳血管障害の患者は、我々の目に見えるのは麻痺という身体的な症状であっても、患者・家族は精神的、社会的、spiritualな苦痛と苦難があるはずである。
しかし、麻痺という身体的な症状が前面に大きく出ているので、医療従事者はそれ以外の痛みや苦しみに気付かないし、気付こうともしない。たとえ気付いたとしても、医療保険で治療される対象には考えない。まして、家族の苦しみや悩みなどは医療従事者には無関係なことでした。
「Mental Pain」の症状が前面に出ている患者は、強い症状しか見ない従来の医療の考え方から言うと、鬱・適応障害・認知症などの精神科担当の疾患と言うことになる。
しかし、Total Painの視点で見直すと、精神的疾患の患者も、不眠や食欲不振などの身体的症状に加えて、家計の破綻や誤解による人々の差別など社会的苦難、さらには自殺念慮などのspiritualな面での苦痛と苦難があるはずである。これらは精神科医による医療保険での治療の対象とはならなくとも、看護や介護などを含めた広い意味での医療の対象として考慮されなければ、本当の治療にはならないと言う考えである。
同様にSocial Painが強い人々は、従来の考え方からすれば社会的弱者と言われ、医療とは無関係のように取り扱われてきた。しかし路上生活者や落ちこぼれと言われる人々は、アルコール中毒や生活習慣病など身体的症状、そして働けない・栄養不足などの困窮状態から来る社会的苦難、さらに家族を見捨てた罪の意識など、精神的にもspiritualな面でも苦痛と苦難を背負っている。そこで単に経済的な援助のみならず、Total Painの中のSocial Painの要素が強い患者と認識した上での対応が必要となる。
ホスピスでのがん終末期医療を経てソンダース女史は、「がんに限らず、どんな病気の患者でも、その背景には必ず身体的、精神的、社会的、スピリチュアルの4つの苦痛と苦難がある。我々が病人あるいは患者と呼んでいる人々の身体的疾患とは、4つの要因の内、身体的苦痛の部分が大きいに過ぎない」。だから「Total Painを緩和するTotal Careこそ医療の本質である」として、これをホスピス運動(Hospice Movement)と命名し、1980年初めから普及活動を行っている。
本邦と異なり、欧米ではTotal Painの概念は、がんに限定されず、AIDZや神経難病などの対応systemとしても、その守備範囲を広げて来た。
しかし、それ以上に評価されるのは、医療従事者中心の医療や疾患の治癒だけを目指してきた医療の在り方自体の変革を目的とするホスピス運動(Hospice Movement)として成果を上げてきた事である。
Hospice Movementは、1991年9月にポルトガルのリスボンで開催された第34回世界医師会総会で採択された「患者の権利に関するリスボン宣言」や1995年の「パリ宣言」を生みだした。これらが、患者の決定権の尊重やinformed consentなどに繋がった。
そして、何と言っても決定的な事は1998年(平成10年)にWHOの健康の定義の改変を促した事である。
従来のWHOの健康の定義が制定されたのは、60年も前の1951年(昭和26年)の事だった。
この時点でも、既に、「健康とは身体的のみならず、精神的・社会的に健やかなる状態」と定義されていた。
1998年にWHO憲章の見直しの一環として健康の定義の変更が検討されることになった。
各国のspiritualに関する宗教的な見解の相違から、批准はまだだが、spiritualの他にも、健康とは流動的であるという意味でdynamicが付記された。
ここで理解してもらいたいのは、spiritualなものとは世界規模で各国を代表する人々が宗教や風俗の違い、言語の壁を乗り越え、わざわざ言葉の定義を決めてまで真剣に討議するような、それ程大切な事柄だと言う事である。
それにも関わらず、本邦ではspiritualについては出来るだけ触れないようにしている。
”がん”や“エイズ”など死に至る病の医療や看護からようやく学んだTotal Painの概念の根本を支えるspiritualという言葉の重みも深さも、畏敬の念も日本人にはないように感じるとのべている。
私はspiritual painとは実存の喪失の時に湧き上がる苦悩だと思っている。Spiritual Painを、魂の痛みあるいは霊的な痛みと考えればその苦悩を救うものは祈りしかにように思う。
在宅ホスピスのすすめ
在宅ホスピスのすすめ
私は2013年3月31日をもって、33年間奉職した綜合病院山口赤十字病院を定年退職する。元気でこれまで勤めることが出来、本当に多くの皆さんにお世話になった。
振り返ってみると、生まれ故郷の山口赤十字病院に就職したのは1979年10月であった。当時、私が生まれ育った仁保の自宅で、母が年老いて一人で生活していた。当時鳥取大学法医学教室にて将来は大学人として実務、研究、教育に携わるか、親の面倒を診るか悩んだ。私を含め5人の子どもを育ててくれた母が、人生最後に一人の生活はあまりにも申し訳ないと思い、当時の吉富院長先生にお話ししたところ、快く「親の面倒を見るなら、喜んで就職を許します。一所懸命に内科学を勉強せよ」とお許しをいただいた。当時の内科には藤本元副院長、為近前院長、昨年お亡くなりになった田中医院の田中先生、鴻城医院の渡邊先生らがおられ、多くの研修をさせていただき、幅広く内科学を学ばせていただいた。内科全般、特に消化器内科の研鑽を積ませていただいた。
1990年、私が診断した直腸がんの一人の患者さんとの出会いが、その後の私のホスピスへの道を拓いてくださったと思う。当時再発転移して次第に衰えて死がみえてきた彼が市民運動で「癌と末期医療を考える会」を立ち上げるにあたり、近代医学の発達と社会の中での病院死が如何に本人、家族にとって多くの苦悩の中でミゼラブルに人生を終えているかを指摘し、もっと人の死を大切にした医療現場を造って欲しいとの訴えに心動かされ、ホスピス緩和ケアをスタートした。1992年に県内で初めての緩和ケア病床をつくり、また、在宅訪問診療(ホスピスケア)をはじめた。当時は訪問看護も、看護ステーションも何も無い時代だった。その後、病院に訪問看護が出来、法律によって訪問看護ステーションが作られてきた。
1999年には全国の日赤で初めての25床の緩和ケア病棟を立ち上げ、今まで5000人近いがん患者、家族と係わり、4000人近い方々を病棟、在宅にて看取らせてもらった。その間、多くの患者さんから生きること、いのちの大切さを学び、これまで3冊の本(ひとひらの死、いのちの響〜ホスピスの春夏秋冬〜、ゆうにゆうにまあるくまあるく)を上梓することができた。
また、2003年全国で初めて行政を巻き込み山口市在宅緩和ケア推進事業に取り組み、年齢制限なく、がんの進行した方の自宅で福祉サービスが受けれるような体制を作ってきた。また、病院の皆様のおかげで、日本で最も伝統のあるホスピスの学会である日本死の臨床研究会の第29回全国大会を2005年に大会長として山口で開催することが出来た。病院の皆様の行動力の素晴らしさに改めて敬服したことを思い出す。
がん拠点病院の指定を受けるために、あるいは臨床研修病院指定を認めていただくために奔走したことを思い出す。一つ一つが自分の使命と考え邁進してきたと思う。振り返ってみると、何もなくとも実践して行動していけばレールは後からできるものだということを学んだ。
今後、自分のライフワークのホスピスを続けたいと考え、新たに4月より山口駅近くで「すえなが内科在宅診療所」を開設して、多くの患者さんの苦悩に寄り添い、在宅ホスピスケアを行なっていくこととした。
我が国では高齢社会の中で、女性の平均寿
命は86歳、男性は80歳となってきた。
しかし、入院医療や施設介護が中心であり、
国民の60%が自宅での療養を望んでいるにもかかわらず、我が家での看取りは12%と低下している。1977年に在宅死から病院死となり、現在は88%が病院死である。
私をホスピスの道に導いた彼は1990年にすでに「近代医学の発達と社会の中での病院死が如何に本人、家族にとって多くの苦悩の中でミゼラブルに人生を終えているか」を指摘していた。
死亡者数は2040年には今より40万人増加する。私のような団塊世代の最終章の人生の締めくくり方が問われているのである。
元気な間は自分で積極的に生き、社会に貢献し、尊厳を保ちながら暮らし続けることが出来るような社会の実現を目指し、高齢者が住み慣れた我が家や地域で自立した生活が出来る事が大切である。そして地域のコミュニティーの中の医療、看護、介護、福祉の連携の中で自分に納得した人生の最終章を生き抜いていくことが大切であると思う。
私たちは天命をいただき、自分の人生を生き抜き、老い、そして人生を締めくくっていかなければいけない。この世の存在は医療や人間の力のおよばない世界である。
いのちを看取るということは残される人、愛する家族、友人がその人と共に歩んだ全人生を看取ることである。看取られる人は苦しさから解放されるが、残される人はそれを乗り越えて生きて行かなければならない。ここに、いのちの連続性があると思う。
日々是好日
日々是好日
中国の禅僧雲門は「心において無事、事において無心なる人の生活は、杞憂を超えて毎日毎日が好日になる」と伝えていると禅聖典に載っている。すなわち良いことも悪いことも、取り巻く現実を徹底して見据えた上で、ここに今、実際に生きて在ることの感謝を知る。そうすれば毎日が好日である。
この言葉を私は記載する事が多い。ホスピスの現場において自らのこの世の存在、すなわち生死(しょうじ)の世界に直面した時に沸き起こってくる根源的な叫びに私たちに何が出来るかという事が問われているのである。ホスピスとは私たちひとり一人がいただいた天命をその瞬間までその人らしく生きるという事に尽きると思う。ホスピスの現場では患者と家族の苦悩を少しでも和らげ、自らのおかれている現実の辛さから目を背けず、自らの人生、いただいた「いのち」に向き合う事が出来る事がとても大切である。そのためには身体的な苦痛からの解放は必要条件にすぎない。ひとり一人が自らのおかれている「いのち」の終焉に肩の力を抜き、重荷を下ろして自らが生きてきた人生に意味を見いだし、納得し、後に託して、心穏やかに安寧な気持ちで今を過ごす事が出来るかが問われているのである。
緩和ケア、緩和医療ということが国の政策として広く認知されているが、その事は入り口の事にすぎないと思う。もっと深いところに私たちの役割があると考える。私たちのこの世の存在が無限の世界からいただいた「いのち」であり、唯一無二の存在であり、誰にも変われない存在であり、そのいただいた「いのち」にはひとり一人に使命があり、ここに存在している事に意味があるということに気づけるような関わりがとても大切である。その事に私たちが如何に寄り添い、ゆっくりした時間の中で架け橋が出来るかという事である。
私たちひとり一人に心の柔らかさがなければいけない。ホスピスの現場で私たちに心にゆとりがなければ、患者や家族への安心感は伝わらない。私はスタッフにいつも心はゴム毬でなければいけない、心は鏡では自らが疲れますよと伝えている。心のゆとりのあることがとても大切なのである。鏡であれば自らが疲れて、よい関わりが出来なくなると考える。
ホスピスの現場は患者・家族が安心して自らの生活の中で今を生きることがとても大切である。生活の中で苦しみがなく、いただいた「いのち」を終えていけるような時間と空間がとても大切である。その場は何処にもあるのである。患者や家族が選択するのは自らが住み慣れた我が家でも病院でも緩和ケア病棟でもいずれの場でもよいと思う。患者・家族が安心して過ごせることが大切なのである。選択は患者・家族にあるのである。私たちはそのシステムが出来るように連携を作っていかなければいけないのである。
ある年老いた母と二人暮らしの息子が不治の病にかかり、懸命に治療に専念するも、次第に病気が進行し、厳しくなってきた。本人は年老いた母に自分の今の状況を知らせたくないという親思う気持ちで、母に会わないできた。年老いた母は姪御さんが一生懸命に面倒をみてあげていた。
彼の病体が厳しくなった時、彼に
「お母さんに一目会ってあげては如何ですか。お母さんに心配をかけないようにという気持ちはよくわかりますが、もし、貴男が亡くなられて、初めて息子の死を知られることは大きな悲しみとなって、嘆かれると思いますよ。貴男も一目お母さんに会って、先に逝くことのつらい気持ちとお母さんへの感謝の気持ちを伝えてあげられと、お母さんの気持ちが少しは安らぐのではないでしょうか」
彼は黙って何も語らなかった。
姪御さんに病状が厳しいことを伝え、年老いた母を連れて来られるように勧めた。
母は息子の病気のことは何もわからない様子であった。母はしきりに息子との生活や家の話をしてくださったが、病状がきわめて厳しくもうすぐお別れになることを伝えた。耳が遠いので理解できない様子であった。息子の手をにぎり、早くよくなって帰って来いよと言われる。私を見つめ手を合わせ、祈るようにされる。彼は母に、もういいよというように自分の口元に指をあて、そっとしておいてという仕草をした。お二人の姿に涙無くして見つめることは出来なかった。そっと、見守ってあげることしか出来ないが、お二人のこころが繋がっていると思った。
吉田松蔭の「親思う心にまさる親心。
今日のおとづれなんと聞くらん」の辞世の句を思い出す。
お二人の悲しみが少しでも癒されることを祈るばかりである。
ホスピスではそれぞれの人生を歩まれた最期にその人の人生を肯定し、まるごと包み込んでくれる人がいることが大切だと思う。
大きな存在のなかのいのち
「大きな存在の中のいのち」
岡部医院を宮城県名取市で1997年開設した岡部健医師は、本格的に在宅緩和ケアを專門とする在宅支援診療所として我国でも草分け的に在宅医療を実践してきた。彼は「緩和ケアは、医療における最終目的の大きな転換であると考えている。緩和ケアの目的は、個々の患者様の残された時間のQOL(生活の質)を最大限に向上させることではないか?緩和ケアは医療だけではなく福祉的側面との複合体である。現状の緩和ケアはホスピス病棟、緩和ケア病棟、病院の中で医師と看護師で行われているが、在宅の中では介護との連携は必須である。QOL評価を軸として、医療と介護の有機的結合をはからなければならないと思う。在宅での死の看取りから看取りの機能を医療者から一般社会に戻し、その中から生まれたタナトロジー(死生学)の形成も重要と考えている」と述べている。1999年には医療グル−プ爽秋会を設立し、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、訪問看護事業所などを併設し、医師、訪問看護師、ケアマネージャー、ヘルパー、薬剤師、作業療法士、ボランティア、チャプレンなどが有機的に関わり、住み慣れた我が家での患者・家族に寄り添う医療、看護、福祉、介護を提供してきた。
その彼が2010に進行胃がんが見つかり、治療を受けながら医療も行ってきた。次第に体力の衰えを感じ始めた2012年6月に彼が私と話がしたいという希望があるという連絡が私のもとに入った。彼とは日本死の臨床研究会や日本ホスピス緩和ケア協会、あるいは講演会などでホスピスや在宅ホスピスケア、死生観などについてこれまでも語る機会はあった。
2012年7月1日に仙台市の彼の自宅を訪れた。
癌性腹膜炎がすすみ、食事がなかなか進まず,痩せが目立っていた彼が玄関まで迎えに出てくれた。応接間のソファーになりながら彼が自分の死生観や我国のホスピスのあり方などを伝えてくれた。彼の語ることばは深い洞察力と日本文化、宗教、医療への幅広い知識が溢れでてきた。その知識の深さに敬服するばかりであった。
医療と医学について医療は、医学と言う科学の限界点を承知した上で行うべき事が必要である。根拠に基づいた医療(Evidence-based medicine、EBM)で悪い事は、観察対象になっていない事象は、存在しない事になってしまう事である。例えば自分が今排便がスムーズにあることがとてもありがたいと感じるが、EBMで排便あり、排便なし、の二つでは、自然排便とはなんと素晴らしい事なんだろうと言う岡部の気持は、存在しない事として、消えてしまう。また、我国では外国のガイドラインや教科書を持ってきて、それを当てはめようとする傾向にある。薬物療法は、世界共通だが、それ以外(緩和医療の項目)はすべて各国で異なっている。介護福祉関係は、法律が異なるし、死生観については文化が異なる。外国のやり方や方法が、日本にそのまま当てはまるわけがない。日本の緩和医療の源流は結核療養所にあると思われるので、そこに求めるのが良く、外国のホスピスに求めるのは間違いではなかろうか。結核の場合は、病名や病状が徹底して伝えられていたから、患者は病気についても、死ぬ事も含めて知っていた。しかし,がんの患者に真実を知らせなかったので(患者が病気について何も知らなかったという点で)、がん治療から始まった日本の緩和医療のあり方は結核療養所とは大きく異なると考えられる。
人間の生き方や人間生活と自然との調和(ecology)まで含むホスピス運動を、医療という狭い世界に閉じ込めたのが、本邦の緩和医療である。そこに間違いがある。
死の方から生き方を見るのは間違いである。生死に関する事柄は、今日を生きるという視点から、結果としてあちらに逝くがん患者の治療やケアを見直すべきである。お葬式の方法や看取りの方法も世界中で、その国により、その地方により、全く別々なのだから、「死」の方から「生」を見れば、バラバラになってしまう。むしろ、人が「生きる」と言う視点から、死を「生死の繋がり、あるいは生の連続帰着点」と考えて対応した方が良い。
人間も自然に生きる地球上にある生物の一つとして、人間を超える大きなものによって、あらかじめ遺伝子に組み込まれている現象の一つとして「お迎え」も「お知らせ」現象も在る、と考えるのが最も素直で、説明が付く考え方だと思われる。お知らせとは遠くの身内に、夢や予兆など何らかの形で現れて自らの死を知らせるような現象をいう。たとえば親父が夢枕に立ったので、急いで帰省したら亡くなったというようなことである・
また、この度の震災の亘理町の荒浜(あらはま)の被災地に立った時に感じたのは、「合理的にものを考えられる場所も、空間も、時間もない、まるで空襲で爆撃を受けた様な状況」だった。
そこに自分の身を曝したら、「ああ、人間と言うのは大きな存在にぶら下がって生きているんだな。個人が集合すると人間になるんじゃないんだ。実は逆なんじゃないか」と思った。この想いは、考えて、得たものではない。ふっと湧いてきた。「あそうか!」と体にストンと落ちてきた。あの場では、物を考えるはずの自我そのものが破綻していた。破綻した時に何が人間の心を支えられたのか、と言ったら、人間とは大きな命に繋がっているもんなんだ。俺が死ぬなんて事は、本当にちっぽけな事なんだ、という様な事が、リアルな感覚として自らの中から湧き出てきた。
これは非常に不思議な感覚だが、被災地に立った多くの人の共通体験でもある。これは集合的無意識論と言うべき現象だと考える。
自分がこのような病気になり、死と対峙する時、人間、病気になって弱ってくると意識が変わる。まず欲求がなくなって、どんどん悪くなるにしたがって植物化する。
体重が強烈に落ちて行く時に、だんだん欲求がなくなって行って、苦痛は無く、生きていたいと言う欲求もなく、いわゆる涅槃に行っちゃう、恐怖も、不安もない。(震災の時に感じた、自分はその一部であると言う)大きな生命体と一緒になっちゃうと言う感覚に近い。死んでいく前に苦痛や恐怖がないというプログラムが人間に組み込まれているとすれば、これは、次の世代に伝達する事はできない(後天的な獲得形質として子孫に伝えることは出来ない)。なぜ、人間に死んでいく前に苦痛や恐怖がないというプログラムがsettingされているんだろう、というと、そこで神様を感じた。
彼は自分の死を前にして感じる事を静かな口調で語りかける。そのことば一つ一つが重く、考えさせられる。
死の臨床における真のホスピスケアを求めて
死の臨床における真のホスピスケアを求めて
私は現在日本死の臨床研究会の顧問をつとめている。日本死の臨床研究会は1977年にスタートした我が国におけるホスピス緩和ケアの最も歴史ある研究会である。その原点は「死の臨床において、患者や家族に対する真の援助の道を全人的立場より研究していくこと」という会の目的にある。2011年度から世話人代表を引き継ぐことになった。
この研究会は約2600名の会員がいる研究会である。年に一度全国大会を行い、北海道から九州まで各ブッロクで支部大会が開催されている。医療関係者だけでなく一般の市民の参加型の研究会であり、学会にしない理由は市民に開けた立ち位置をとり、ひとり一人の「いのち」への向き合いを探求していく学問的研究会を目的としているからである。 医師、看護師、薬剤師、介護福祉士、医療ソーシャルワーカー、僧侶、ボランティア、一般市民など多岐にわたる職種からなる研究会である。
「死の臨床」とは死に直面した時、沸き上がってくる根源的な叫び、すなわち自分のこの世の存在が失われていくという苦悩、言い換えれば不条理な人生を直視したときの深いスピリチュアルぺインの中にある人々への寄り添いだと思う。
スピリチュアルペインとは己の実存の喪失と考える。私たちが生きていく上で最も大切なことは、あるいは生き甲斐とは自分の実存即ちこの世の存在の意味を感じ、生かされている、必要とされていると感じることであると考える。この実存の喪失、生きている意味の喪失こそがスピリチュアルペインだと考える。
ホスピスとは目の前に悩める人にいかに手をさしのべるかという哲学であり、私たち一人ひとりがいただいた「いのち」をその人らしく生ききることであり、医療をはるかに超えた「いのち」の尊厳を大切にすることだと考えている。
すべての人々はその苦悩の中で、その瞬間まで今を生きている。私たちがその専門性を生かし、チームとして患者・家族の皆様の心の架け橋や燈明を照らすことができるかが問われているのだと思う。死の臨床においてすべての人々が自分の人生に意味を見出し、価値を見出して安寧な気持ちで終えていけるようにありたいものである。
私たち一人ひとりは無限の世界からこの世に生を受け、人生を歩み、また無限の世界に戻らざるを得ない。どのような人生を歩もうとも、一人ひとりの人生には必ずキラリと光るものがあり、存在することそのことに意味がある。この二度とない人生をその瞬間まで実存を感じられるような場がとても大切だと思う。ホスピスの場とは悪くて、だめだから行く最期の場ではなく、その瞬間までより良く生きる場であり、それを支え、橋渡しをする場である。そのために、時間と空間がとても大切な場であり、いのちを通じて生きるということを考え、学ぶ場だと思う。病院でもホスピス緩和ケア病棟でも住み慣れた我が家でも患者さんとそのご家族が安心して最期まで過ごせることが大切なのだと思う。
そして、看取りとはその人が歩んだ全人生を看取ることであり、その看取りが出来るのは共に歩んだ家族や親族や友人などだと思いう。最期のいのちは家族にお返ししなければいけない。第35回死の臨床研究会の大会長の蘆野・長澤両会長がご挨拶の中で「学びの場である看取りを、非日常性の医療の場から日常の生活の場、あるいは日常的な環境になるように配慮した場に移すこと、医療者ではなく家族や親族あるいは友人などが看取るように配慮すること、地域社会が看取りを支援することが、今重要であると考えます」と言われている。この研究会の原点だと思う。
がん対策基本法に基づき、国民に広く緩和ケアの普及・啓発がなされ、医療的な面では進歩し続けている。しかし、金城学院大学学長の柏木先生のいわれる人の死は医学的出来事ではなく、人間学的出来事であり、社会学的出来事であるということである。
医療の進歩に伴い多くの恩恵がもたらされているが、人の死は決して医療では救えない。この世の存在は医療とか人間の力では及ばないことに気づかなければいけない。現代医療のアンチテーゼとして死の臨床研究会が産声を上げた原点を噛み締めなければいけないと考える。
今後、我が国を取り巻く環境はますます複雑化してきている。少子高齢化の中で、多死社会の中で一人ひとりの人生の生き方や終え方の価値観も変化し、多様化してくる。
医療、看護、介護、福祉の現場で、一人ひとりのいのちを大切にする智恵と工夫がますます重要になってくる。日本死の臨床研究会がなすべき役割は現場の実践を生かし、実践活動の学びの場となり、広い視野にたって益々発展していく事が大切であると考える。
死とは忌み嫌うものではなく、人生をやり終えた、あるいは自分の人生に納得し、後に託し、安寧な気持ちで終えていくという温かいものでなければいけないと考える。そんな生き方がとても大切だと思う。
今日も病棟で若い30代の若者が意識無く、ケアを受けている。その奥様と二人の小さな子どもたちがそばで過ごされ、普通の生活の営みがなされている。子どもは幼稚園にも病室から通っている。ここが家なのである。そこにはいのちの息吹が感じられる。いのちがとても愛おしく、ここに存在することに意味があるのである。私たちは今、ここに存在していることがすばらしいことに気づかなければいけない。
緩和ケアの取り組みとホスピスのこころ
緩和ケアの取り組みとホスピスのこころ
山口県のホスピス緩和ケアの歴史は1990年「がんと末期医療を考える会」が発足し、主宰の岡博氏が自らのがんの闘病を通じて「末期医療の充実とは何か。一言で言って人間の死を尊重してくれるということだ。現在、病院でいったい何人の人々がよく生き得、良く死に得ているでしょうか。懸命に生きてきた人生の場所が昭和二十三年の基準によるわずか二、六畳というベッド空間。プライバシーは全く認められず、他の患者の鼾やおなら、時には糞尿の臭い、同室者との人間関係を保つための妥協や追従。なに一つ思うようにならず、家族は肩身狭く付き添う病院の大部屋であるとは!」との訴えに触発され、私たちが院内に「ターミナルケア研究会」を設立したのがスタートです。1992年には県内で初めての3床の緩和ケア病床を設置し、本格的に取り組み始めました。その後、東病棟の建設に伴い、最上階に25床の承認施設としての緩和ケア病棟を1999年11月にスタートすることができました。日本赤十字社93病院の中で初めての緩和ケア病棟でした。開設記念講演に柏木哲夫先生に来ていただき、10周年開設記念に再び柏木先生にお出でいただくことができ、本当に嬉しく思います。1992年の緩和ケア病床をスタートした時点から我が家で最期を過ごしたいという患者の希望に添って、在宅ホスピスケアも行ってきました。患者さんやご家族が安心して過ごせる療養の場を提供するべき、入院,在宅,外来を三位一体としてシステム化することが大切であると考えて行動してきました。その結果、全国に先駆け山口市の行政の力を借りて2003年に山口市在宅緩和ケア推進事業を開始し、年齢制限なく1割の自己負担で福祉サービスが受けられる体制を造ってきました。その後、2004年山口市在宅緩和ケア支援センター開始。笹川医学医療研究財団ホスピスナース研修施設となり、2007年には日本医療機能評価機構付加機能評価緩和ケア機能認定を受けました。また、山口県在宅緩和ケア対策推進事業開始に伴い、山口県在宅緩和ケア支援センターを設置、2008年院内緩和ケアチームを開始しました。
このような歴史を振り返ってみて、何も無いところからスタートして苦節20年、感慨無量です。振り返ってみるに軌跡はあとから出来て来ることをつくづく感じます。いつも物事は成就出来るという信念のもとで歩み続けてまいりました。
今一番心配しておりますことはホスピスが次第に医療化していく我が国の現状をかんがみ、今一度ホスピスの意味を問い直さなければいけないと痛感しています。
ホスピス・緩和ケア病棟がスタートしたのは現代の病院死の中での人の死の尊厳があまりにもおろそかにされてきた経緯の中で、あるいは人の死の医学化の中で、身体的な生命のみに重きをおき、「いのち」としてのトータルケアを失ったことへのアンチテーゼとしてスタートしているのです。
良く考えてみるに私たちは天命をいただいているのです。すべての医療行為は延命のために行われ、天命を全うするためになされているのです。しかし、私たちがいただいたこの世の存在は医療や人間の力のおよばない世界であることに気づかなければいけません。
ホスピスの本質は目の前に悩める人にいかに手をさしのべるかという哲学であり、私たち一人一人がいただいた「いのち」をその人らしく生ききることであり、医療をはるかに超えた「いのち」の尊厳を大切にすることです。「死を看取る」ことは「生きること」を学ぶことであり、無限な世界からいただいたこの世の有限な「いのち」がふたたび無限の世界へ還って行くことへの場の提供です。人間存在における苦悩は生死(しょうじ)の世界に直面して沸き上がってくる根源的な叫びにたいして、内なる世界すなわち自分の生きてきた人生に意味、価値があることに気づき、その瞬間まで生きていることの喜びを感じるとともに、絶対世界すなわち大いなる力にゆだね、安寧な気持ちでこの世を終えていけるような架け橋の場がホスピスなのです。身体症状緩和は必要条件であり、ライセンスを持つ医療従事者は義務なのです。しかし、ホスピスの求められているのは生死(しょうじ)の世界への対応であり、悩める人に燈明(とうみょう)を照らすことであると思います。そのためにも医療従事者は自らの死生観,人生観などをしっかり築いていかなければいけないと考えます。
ホスピス・緩和ケアのこころ
ホスピス・緩和ケアのこころ
多くの人びとが生命を脅かす疾患に直面したとき、患者さんもご家族も同じ苦しみに見舞われます。特にがんと診断されたときから、患者さんもご家族も心はゆらぎの連続です。がんの進行や再発の不安を抱えながら、希望を見いだしたいと思いながら、日々の療養を続けておられます。身体的な苦しみがあると希望は見いだされなくなります。また、ご家族のこと経済的なことにも思い悩まれます。ご家族もその苦しみは同じなのです。治ってほしい、元気でいてほしいと願い続けられます。そして、スピリチュアル、魂のさけびがいつも不安となって頭をもたげてきます。いつまで生きられるのだろうかという将来への希望が見いだせなくなり、愛する家族や人生をともに歩んだ人と別れなければならないという不安、そして自分で自分のことができなくなり、この世にいただいた「いのちの存在」そのものに向きあわざるをえなくなります。その時私たちは何ができるのでしょうか。悩まれ苦しみにある患者さんやご家族の方の足下にそっと灯りをかざすことではないでしょうか。温かい心の通い合いであり、患者さんとご家族の不安に寄り添い、薄明るい歩むべき道筋が見えてくるように傍らに立つことではないでしょうか。ホスピスは悪くて、だめだから行く最後の場ではなく、その瞬間までより良く生きる場であり、患者さんとご家族を支え、橋渡しをする場であると思います。辛さを受け入れていくことはとても時間がかかります。一つ一つの希望が少しずつ削ぎ落とされていきます。これを自分で受け止めて行くにはとても時間がかかります。受け入れられなく、諦めになっていくことも多くあります。患者さんの苦しみに寄り添われるご家族には共に過ごす時間と空間がとても大切な場になるのです。ご家族の悲嘆が大きくならないように患者さんとご家族のこころの架け橋がとても大切だと思います。そして、ホスピスの場は患者さんがその瞬間まで生ききられ、寄り添われる家族はそのいのちを通じて生きるということを考え、乗り越えて、いただいた自らのいのちを生きるということを学ばれる場だと思います。そして、患者さんやご家族が辛いときに辛いと言え、孤独にしないように寄り添って行くことが問われていると思います。その瞬間まで自分のいただいた人生に意味を見いだされ、納得できるように、また安心して後に託すことができるような寄り添いと架け橋を大切にした、そのようなホスピスでありたいと思います。
在宅の良さは医療目線にならない、生活の中での存在であり、管理からの脱却であると考えます。多くのチームの協働により、患者・家族に寄り添い、生きる希望を見出し、その瞬間まで自立を支援し、皆様の尊厳性を大切にした関わりだと思います。2次元の世界から3次元の世界へ、ベッドから屋内へそして屋外へ、生活空間を広げ、今ここに生きているということを感じ、天の恵みの中で、家族の愛の中で、多くのチームの協働の中でその瞬間まで実存を感じ、ゆっくりした時間の中でいのちを見つめ合う事ができていくのです。在宅ケアは人間らしく生きるということの最も大切な希望につながる支援だと思います。
✕
院長 コラム
和解と懺悔
和解と懺悔
「身体的に辛い中で、自分の良いところに目を向けて、前を向いていきましょう」とベッドサイドでお話しすると、彼から
「光の見えない者に、何が出来るか」と強い調子で言葉が戻ってきた。
廊下にでて
ああ、そうか。光が見えないとは生きる希望が持てないということなのだ。生きる希望が持てないのに前を向くことも、そのような気持ちにもなれないといわれている。私の言葉が如何に空虚に感じられたことかと思い、廊下を歩きながら、自らの言葉の罪深さを思い、私の言葉が頭の中をぐるぐると回り続けた。私はじくじたる思いに駆られた。
彼はまだ50歳代であった。がんを患い、他の医療機関で治療を受け続けてきたが、呼吸も苦しくなり、言葉を発するのも次第に難しくなっていた。すべてが受け入れられず、すべてを拒否され、ベッドに臥床し、カーテンを閉め、食事も摂らず、終日起きることもなく、看護師のケアも受け入れないという状態であった。自暴自棄的ですべてを拒否するというものであった。
私がベッドサイドに診察に向かっても、会話は成立せず、背を向け布団をかぶったままであった。お姉さんが傍にいたが、私にすまなさそうな表情を浮かべていた。
数日後、夕方ベッドサイドに行くと、別れた奥さんが来ていた。彼と奥さんとの会話はその場に居合わせないので知る由もなかった。しかし、その日を境に彼の表情、行動に変化が見られ始めた。
奥さんの押す車椅子に乗って、自室から廊下に出はじめた。デールームから花の咲いているベランダにでて、外の景色を眺め、山の彼方を静かに眺めていた。山並みの彼方には自分の生活している村がある。大きく深呼吸をした。青空にはぽっかり白い雲が浮かんでいた。奥さんと言葉を交わす姿がみえた。ベランダから眺めている彼の後ろ背に奥さんが静かに語りかけていた。
彼は孤独で寂しかったのである。
彼は家庭内暴力で奥さんも離婚し、娘も離れていっていたのである。自分が自らまねいた結果であった。
自らが病の床に伏し、次第に自らの置かれた病状の変化に気づき、相談する者もなく、こころの辛さに寄り添ってくれる者は姉さん以外誰もいなかった。
そのような時、最初の言葉がほとばしり出たのである。
「光のみえない者に何が出来るか」
彼は寂しく、切なく、自らの死と向き合い、すべてのことが受け入れられなかったのである。
その時、別れた奥さんが彼のもとにある日の夕方来たのである。多分姉さんが奥さんに連絡したのであろう。
その時の彼と奥さんの会話は知る由もないが、彼の変化で理解することが出来た。
たぶん彼は奥さんに
「ごめん。悪かった。俺を許してくれ。苦労をかけてすまなかった。娘にも父として何もしてやらず、本当にすまなかった。許してくれ」
彼のこころからの懺悔の言葉が迸り出たのではないか。
奥さんがそれを許してあげられたのでしょう。
彼の長年月の積もり積もった心の重荷が少しずつ緩んできたのであろう。彼の病床での変化が起こってきた。全く拒絶していた食事にも少しずつ向かい、奥さんの押す車椅子で自分の部屋から外に出るまでに心が変化してきたのである。
人間は自分の人生を歩む。縁の中で自分の人生を歩むのである。自分がどんな人生を歩もうとも、自分の選択で、決断で行動しているのである。一期一会の中で自らが何を掴み、何を行い、何を幸せと感じるかは、ひとえに己の心のなかにあるのである。泣くも、笑うも,悦ぶも、悩むも心一つなのである。自らの因縁によって目の前の結果があり、自我に固執すれば畢竟苦の中にあるが、それを苦と感じるか、幸せと感じるかは心一つなのである。
多くの患者・家族との出会いから、多くのことを学ばせていただいている。その中で、生死の世界に直面した時、一生懸命生きてきた人生に意味があり、納得して、後に託し、安寧な心になれるかがとても大切であると感じる。過去を背負い、今を生き、現世の肩の重荷を下ろして、永劫の未来へ向かって歩んでいただきたいとつくづく思う。私は「燈明を照らす」ことが大切と思っている。多くの苦悩ある人々の足元にそっと明かりを照らすことができ、ひとり一人が自らの生死の世界から目を離さず、自らが諦観され、心穏やかになっていただきたいと祈るばかりである。ひとえに自らの心のあり方と思われる。
彼は数週間、奥様やお姉さんの支えの中で過ごされていた。次第に身体的な限りがみえてきた時、
「もういいよ。本当に皆にお世話になった。もう思い残すことはない。身体も本当に辛くなったので、そっと旅立って行きたい。よろしく頼むよ」と私にかすれる声で言った。
彼のこの世の生きてきた人生の中で、最期に肩の重い荷物を下ろすことができ、心穏やかに旅立っていかれたと思えてならない。奥様のおかげである。奥様も彼の最期の懺悔に心の中に明かりが灯ったことだろう。
祈り
祈り
我が国におけるspiritualの意味すること
皆さんはspiritual pain、spiritual careなどの言葉を聞かれたことがあるだろうか。
元東北大学医学部麻酔・救急医学講座疼痛制御科学分野教授で現在八戸看護専門学校校長の山室誠先生から我国におけるspiritualへの概念について私に意見を求められた。先生は医療におけるspiritual pain、spiritual care等について書簡をくださった。
その中で
2012年、春の高校野球の開会式での石巻工業高校、阿部翔人(しょうと)君の選手宣誓は、被災者が苦しんでいるのはspiritual painであることを全身全霊で受け止めているものであった。
チームのメンバーの中にも身内を亡くした人、家が流された選手も居たが、そんな彼らが、支援活動にいそしみながら作り上げた宣誓文でした。
「被災された方の中には、苦しくて心の整理が付かず、今も当時のことや、亡くなられた方が忘れられず、悲しみに暮れている方がたくさん居ます。人は誰でも、答えのない悲しみを受け入れることは苦しくて辛いことです」
彼ら自身は、Spiritual Painなどという言葉を知らなかったと思うが、この宣誓文に勝るSpiritual Painの説明はないと思ったと述べられている。
私たちが日常生活の中で病気もせず、家庭も円満で、自分の仕事に邁進して身体的にも精神的にも社会的にも落ち着いているときにはあまり深く考えることもない。このような生活の中で破れが生じた時、例えば病気になり、生死の世界に直面した時、会社が倒産して自分の日々の生活を真剣に考えなければいけなくなった時、心が病み日々の生活がこなせなくなってきた時、
どうして、自分が「がん」になったのだろう?
他人ではなく、何故、私が被災者になったのだろう?
何もかも失ってしまった今から生きて行く価値があるのだろうか?
どうして私ではなく、あの人が死んでしまったのだろう?
なぜ私がいじめられなければいけないのか?
というような思いが頭をもたげてくる。
これがspiritual painと言われるものである。「不条理で答えのない自らへの問いに、苦しみながらも何とか人間として生きていくための存在能力に関わる事柄」だと考えられる。
日本のホスピス関連の第1人者である、金城学院学院長の柏木哲夫先生は、精神科医として、「苦痛や苦難が“心の病”で留まっている間は“欝”の対応でよいが、“魂”の病気になると“自殺念慮”が出てくるように思うと言われた。
山室先生は書簡の中で次のように述べている。また「Spiritual Pain」が、“死に至る病のTotal Painの構成因子”であることから考えて、spiritual painとは
「希死願望を起こさせるような苦痛と苦難」と考えられる。さらに希死願望とは、生きる価値と生きる意味と生きる目的を失った場合に生じると言われる。
がん終末期患者の「死ぬのが怖い」「死にたくない」と言うのも、逆説的な表現で、広い意味での希死願望に入るそうである。
したがってSpiritual Careとは、希死願望を喪失させるためのCare、すなわち生きる価値と生きる意味と生きる目的を実感して「こんなに苦しい“にも関わらず”、今は生きて行く望みも見当たらない“にも関わらず”生きる、生きて行こう」と言う想いを起こさせるような支援や対応と言うことになる。
そして、これらの支援や対応を「Spiritual Care」と言い、「Spiritual Care」により、「Spiritual Pain」が解消される事が「癒し」(Healing)になる。
医療の現場、特にホスピス緩和医療分野ではTotal Painという言葉が使われる。日本語では「全人格的疼痛」あるいは片仮名で「トータルペイン」と言われている。
近代ホスピスの母と言われるシシリー・ソンダース女史が提唱された概念であるが、Painと言う言葉は痛みに限定されず、「自分には重荷だ」とか「辛い」というような意味でも、It’s my Pain などと言うと述べている。苦痛としては身体的な痛み(physical pain)、精神的な痛み(mental pain)がある。さらに痛みと言うよりは苦難と捉えた方が理解しやすい社会的な痛み(social pain)がある。これは病気による失職とか借金による家計の破綻など経済的な苦難、家族が背負う労力的、時間的な負担など、社会的な問題から起こる苦しみを言う。4つ目がSpiritual Painである。この概念が紹介された当初は、宗教的な痛みとか魂の痛みなどと訳された事もあるが、緩和医療の分野では、「スピリチュアル」と、そのまま片仮名で表記することにした。たとえば、脳血管障害の患者は、我々の目に見えるのは麻痺という身体的な症状であっても、患者・家族は精神的、社会的、spiritualな苦痛と苦難があるはずである。
しかし、麻痺という身体的な症状が前面に大きく出ているので、医療従事者はそれ以外の痛みや苦しみに気付かないし、気付こうともしない。たとえ気付いたとしても、医療保険で治療される対象には考えない。まして、家族の苦しみや悩みなどは医療従事者には無関係なことでした。
「Mental Pain」の症状が前面に出ている患者は、強い症状しか見ない従来の医療の考え方から言うと、鬱・適応障害・認知症などの精神科担当の疾患と言うことになる。
しかし、Total Painの視点で見直すと、精神的疾患の患者も、不眠や食欲不振などの身体的症状に加えて、家計の破綻や誤解による人々の差別など社会的苦難、さらには自殺念慮などのspiritualな面での苦痛と苦難があるはずである。これらは精神科医による医療保険での治療の対象とはならなくとも、看護や介護などを含めた広い意味での医療の対象として考慮されなければ、本当の治療にはならないと言う考えである。
同様にSocial Painが強い人々は、従来の考え方からすれば社会的弱者と言われ、医療とは無関係のように取り扱われてきた。しかし路上生活者や落ちこぼれと言われる人々は、アルコール中毒や生活習慣病など身体的症状、そして働けない・栄養不足などの困窮状態から来る社会的苦難、さらに家族を見捨てた罪の意識など、精神的にもspiritualな面でも苦痛と苦難を背負っている。そこで単に経済的な援助のみならず、Total Painの中のSocial Painの要素が強い患者と認識した上での対応が必要となる。
ホスピスでのがん終末期医療を経てソンダース女史は、「がんに限らず、どんな病気の患者でも、その背景には必ず身体的、精神的、社会的、スピリチュアルの4つの苦痛と苦難がある。我々が病人あるいは患者と呼んでいる人々の身体的疾患とは、4つの要因の内、身体的苦痛の部分が大きいに過ぎない」。だから「Total Painを緩和するTotal Careこそ医療の本質である」として、これをホスピス運動(Hospice Movement)と命名し、1980年初めから普及活動を行っている。
本邦と異なり、欧米ではTotal Painの概念は、がんに限定されず、AIDZや神経難病などの対応systemとしても、その守備範囲を広げて来た。
しかし、それ以上に評価されるのは、医療従事者中心の医療や疾患の治癒だけを目指してきた医療の在り方自体の変革を目的とするホスピス運動(Hospice Movement)として成果を上げてきた事である。
Hospice Movementは、1991年9月にポルトガルのリスボンで開催された第34回世界医師会総会で採択された「患者の権利に関するリスボン宣言」や1995年の「パリ宣言」を生みだした。これらが、患者の決定権の尊重やinformed consentなどに繋がった。
そして、何と言っても決定的な事は1998年(平成10年)にWHOの健康の定義の改変を促した事である。
従来のWHOの健康の定義が制定されたのは、60年も前の1951年(昭和26年)の事だった。
この時点でも、既に、「健康とは身体的のみならず、精神的・社会的に健やかなる状態」と定義されていた。
1998年にWHO憲章の見直しの一環として健康の定義の変更が検討されることになった。
各国のspiritualに関する宗教的な見解の相違から、批准はまだだが、spiritualの他にも、健康とは流動的であるという意味でdynamicが付記された。
ここで理解してもらいたいのは、spiritualなものとは世界規模で各国を代表する人々が宗教や風俗の違い、言語の壁を乗り越え、わざわざ言葉の定義を決めてまで真剣に討議するような、それ程大切な事柄だと言う事である。
それにも関わらず、本邦ではspiritualについては出来るだけ触れないようにしている。
”がん”や“エイズ”など死に至る病の医療や看護からようやく学んだTotal Painの概念の根本を支えるspiritualという言葉の重みも深さも、畏敬の念も日本人にはないように感じるとのべている。
私はspiritual painとは実存の喪失の時に湧き上がる苦悩だと思っている。Spiritual Painを、魂の痛みあるいは霊的な痛みと考えればその苦悩を救うものは祈りしかにように思う。
在宅ホスピスのすすめ
在宅ホスピスのすすめ
私は2013年3月31日をもって、33年間奉職した綜合病院山口赤十字病院を定年退職する。元気でこれまで勤めることが出来、本当に多くの皆さんにお世話になった。
振り返ってみると、生まれ故郷の山口赤十字病院に就職したのは1979年10月であった。当時、私が生まれ育った仁保の自宅で、母が年老いて一人で生活していた。当時鳥取大学法医学教室にて将来は大学人として実務、研究、教育に携わるか、親の面倒を診るか悩んだ。私を含め5人の子どもを育ててくれた母が、人生最後に一人の生活はあまりにも申し訳ないと思い、当時の吉富院長先生にお話ししたところ、快く「親の面倒を見るなら、喜んで就職を許します。一所懸命に内科学を勉強せよ」とお許しをいただいた。当時の内科には藤本元副院長、為近前院長、昨年お亡くなりになった田中医院の田中先生、鴻城医院の渡邊先生らがおられ、多くの研修をさせていただき、幅広く内科学を学ばせていただいた。内科全般、特に消化器内科の研鑽を積ませていただいた。
1990年、私が診断した直腸がんの一人の患者さんとの出会いが、その後の私のホスピスへの道を拓いてくださったと思う。当時再発転移して次第に衰えて死がみえてきた彼が市民運動で「癌と末期医療を考える会」を立ち上げるにあたり、近代医学の発達と社会の中での病院死が如何に本人、家族にとって多くの苦悩の中でミゼラブルに人生を終えているかを指摘し、もっと人の死を大切にした医療現場を造って欲しいとの訴えに心動かされ、ホスピス緩和ケアをスタートした。1992年に県内で初めての緩和ケア病床をつくり、また、在宅訪問診療(ホスピスケア)をはじめた。当時は訪問看護も、看護ステーションも何も無い時代だった。その後、病院に訪問看護が出来、法律によって訪問看護ステーションが作られてきた。
1999年には全国の日赤で初めての25床の緩和ケア病棟を立ち上げ、今まで5000人近いがん患者、家族と係わり、4000人近い方々を病棟、在宅にて看取らせてもらった。その間、多くの患者さんから生きること、いのちの大切さを学び、これまで3冊の本(ひとひらの死、いのちの響〜ホスピスの春夏秋冬〜、ゆうにゆうにまあるくまあるく)を上梓することができた。
また、2003年全国で初めて行政を巻き込み山口市在宅緩和ケア推進事業に取り組み、年齢制限なく、がんの進行した方の自宅で福祉サービスが受けれるような体制を作ってきた。また、病院の皆様のおかげで、日本で最も伝統のあるホスピスの学会である日本死の臨床研究会の第29回全国大会を2005年に大会長として山口で開催することが出来た。病院の皆様の行動力の素晴らしさに改めて敬服したことを思い出す。
がん拠点病院の指定を受けるために、あるいは臨床研修病院指定を認めていただくために奔走したことを思い出す。一つ一つが自分の使命と考え邁進してきたと思う。振り返ってみると、何もなくとも実践して行動していけばレールは後からできるものだということを学んだ。
今後、自分のライフワークのホスピスを続けたいと考え、新たに4月より山口駅近くで「すえなが内科在宅診療所」を開設して、多くの患者さんの苦悩に寄り添い、在宅ホスピスケアを行なっていくこととした。
我が国では高齢社会の中で、女性の平均寿
命は86歳、男性は80歳となってきた。
しかし、入院医療や施設介護が中心であり、
国民の60%が自宅での療養を望んでいるにもかかわらず、我が家での看取りは12%と低下している。1977年に在宅死から病院死となり、現在は88%が病院死である。
私をホスピスの道に導いた彼は1990年にすでに「近代医学の発達と社会の中での病院死が如何に本人、家族にとって多くの苦悩の中でミゼラブルに人生を終えているか」を指摘していた。
死亡者数は2040年には今より40万人増加する。私のような団塊世代の最終章の人生の締めくくり方が問われているのである。
元気な間は自分で積極的に生き、社会に貢献し、尊厳を保ちながら暮らし続けることが出来るような社会の実現を目指し、高齢者が住み慣れた我が家や地域で自立した生活が出来る事が大切である。そして地域のコミュニティーの中の医療、看護、介護、福祉の連携の中で自分に納得した人生の最終章を生き抜いていくことが大切であると思う。
私たちは天命をいただき、自分の人生を生き抜き、老い、そして人生を締めくくっていかなければいけない。この世の存在は医療や人間の力のおよばない世界である。
いのちを看取るということは残される人、愛する家族、友人がその人と共に歩んだ全人生を看取ることである。看取られる人は苦しさから解放されるが、残される人はそれを乗り越えて生きて行かなければならない。ここに、いのちの連続性があると思う。
日々是好日
日々是好日
中国の禅僧雲門は「心において無事、事において無心なる人の生活は、杞憂を超えて毎日毎日が好日になる」と伝えていると禅聖典に載っている。すなわち良いことも悪いことも、取り巻く現実を徹底して見据えた上で、ここに今、実際に生きて在ることの感謝を知る。そうすれば毎日が好日である。
この言葉を私は記載する事が多い。ホスピスの現場において自らのこの世の存在、すなわち生死(しょうじ)の世界に直面した時に沸き起こってくる根源的な叫びに私たちに何が出来るかという事が問われているのである。ホスピスとは私たちひとり一人がいただいた天命をその瞬間までその人らしく生きるという事に尽きると思う。ホスピスの現場では患者と家族の苦悩を少しでも和らげ、自らのおかれている現実の辛さから目を背けず、自らの人生、いただいた「いのち」に向き合う事が出来る事がとても大切である。そのためには身体的な苦痛からの解放は必要条件にすぎない。ひとり一人が自らのおかれている「いのち」の終焉に肩の力を抜き、重荷を下ろして自らが生きてきた人生に意味を見いだし、納得し、後に託して、心穏やかに安寧な気持ちで今を過ごす事が出来るかが問われているのである。
緩和ケア、緩和医療ということが国の政策として広く認知されているが、その事は入り口の事にすぎないと思う。もっと深いところに私たちの役割があると考える。私たちのこの世の存在が無限の世界からいただいた「いのち」であり、唯一無二の存在であり、誰にも変われない存在であり、そのいただいた「いのち」にはひとり一人に使命があり、ここに存在している事に意味があるということに気づけるような関わりがとても大切である。その事に私たちが如何に寄り添い、ゆっくりした時間の中で架け橋が出来るかという事である。
私たちひとり一人に心の柔らかさがなければいけない。ホスピスの現場で私たちに心にゆとりがなければ、患者や家族への安心感は伝わらない。私はスタッフにいつも心はゴム毬でなければいけない、心は鏡では自らが疲れますよと伝えている。心のゆとりのあることがとても大切なのである。鏡であれば自らが疲れて、よい関わりが出来なくなると考える。
ホスピスの現場は患者・家族が安心して自らの生活の中で今を生きることがとても大切である。生活の中で苦しみがなく、いただいた「いのち」を終えていけるような時間と空間がとても大切である。その場は何処にもあるのである。患者や家族が選択するのは自らが住み慣れた我が家でも病院でも緩和ケア病棟でもいずれの場でもよいと思う。患者・家族が安心して過ごせることが大切なのである。選択は患者・家族にあるのである。私たちはそのシステムが出来るように連携を作っていかなければいけないのである。
ある年老いた母と二人暮らしの息子が不治の病にかかり、懸命に治療に専念するも、次第に病気が進行し、厳しくなってきた。本人は年老いた母に自分の今の状況を知らせたくないという親思う気持ちで、母に会わないできた。年老いた母は姪御さんが一生懸命に面倒をみてあげていた。
彼の病体が厳しくなった時、彼に
「お母さんに一目会ってあげては如何ですか。お母さんに心配をかけないようにという気持ちはよくわかりますが、もし、貴男が亡くなられて、初めて息子の死を知られることは大きな悲しみとなって、嘆かれると思いますよ。貴男も一目お母さんに会って、先に逝くことのつらい気持ちとお母さんへの感謝の気持ちを伝えてあげられと、お母さんの気持ちが少しは安らぐのではないでしょうか」
彼は黙って何も語らなかった。
姪御さんに病状が厳しいことを伝え、年老いた母を連れて来られるように勧めた。
母は息子の病気のことは何もわからない様子であった。母はしきりに息子との生活や家の話をしてくださったが、病状がきわめて厳しくもうすぐお別れになることを伝えた。耳が遠いので理解できない様子であった。息子の手をにぎり、早くよくなって帰って来いよと言われる。私を見つめ手を合わせ、祈るようにされる。彼は母に、もういいよというように自分の口元に指をあて、そっとしておいてという仕草をした。お二人の姿に涙無くして見つめることは出来なかった。そっと、見守ってあげることしか出来ないが、お二人のこころが繋がっていると思った。
吉田松蔭の「親思う心にまさる親心。
今日のおとづれなんと聞くらん」の辞世の句を思い出す。
お二人の悲しみが少しでも癒されることを祈るばかりである。
ホスピスではそれぞれの人生を歩まれた最期にその人の人生を肯定し、まるごと包み込んでくれる人がいることが大切だと思う。
大きな存在のなかのいのち
「大きな存在の中のいのち」
岡部医院を宮城県名取市で1997年開設した岡部健医師は、本格的に在宅緩和ケアを專門とする在宅支援診療所として我国でも草分け的に在宅医療を実践してきた。彼は「緩和ケアは、医療における最終目的の大きな転換であると考えている。緩和ケアの目的は、個々の患者様の残された時間のQOL(生活の質)を最大限に向上させることではないか?緩和ケアは医療だけではなく福祉的側面との複合体である。現状の緩和ケアはホスピス病棟、緩和ケア病棟、病院の中で医師と看護師で行われているが、在宅の中では介護との連携は必須である。QOL評価を軸として、医療と介護の有機的結合をはからなければならないと思う。在宅での死の看取りから看取りの機能を医療者から一般社会に戻し、その中から生まれたタナトロジー(死生学)の形成も重要と考えている」と述べている。1999年には医療グル−プ爽秋会を設立し、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、訪問看護事業所などを併設し、医師、訪問看護師、ケアマネージャー、ヘルパー、薬剤師、作業療法士、ボランティア、チャプレンなどが有機的に関わり、住み慣れた我が家での患者・家族に寄り添う医療、看護、福祉、介護を提供してきた。
その彼が2010に進行胃がんが見つかり、治療を受けながら医療も行ってきた。次第に体力の衰えを感じ始めた2012年6月に彼が私と話がしたいという希望があるという連絡が私のもとに入った。彼とは日本死の臨床研究会や日本ホスピス緩和ケア協会、あるいは講演会などでホスピスや在宅ホスピスケア、死生観などについてこれまでも語る機会はあった。
2012年7月1日に仙台市の彼の自宅を訪れた。
癌性腹膜炎がすすみ、食事がなかなか進まず,痩せが目立っていた彼が玄関まで迎えに出てくれた。応接間のソファーになりながら彼が自分の死生観や我国のホスピスのあり方などを伝えてくれた。彼の語ることばは深い洞察力と日本文化、宗教、医療への幅広い知識が溢れでてきた。その知識の深さに敬服するばかりであった。
医療と医学について医療は、医学と言う科学の限界点を承知した上で行うべき事が必要である。根拠に基づいた医療(Evidence-based medicine、EBM)で悪い事は、観察対象になっていない事象は、存在しない事になってしまう事である。例えば自分が今排便がスムーズにあることがとてもありがたいと感じるが、EBMで排便あり、排便なし、の二つでは、自然排便とはなんと素晴らしい事なんだろうと言う岡部の気持は、存在しない事として、消えてしまう。また、我国では外国のガイドラインや教科書を持ってきて、それを当てはめようとする傾向にある。薬物療法は、世界共通だが、それ以外(緩和医療の項目)はすべて各国で異なっている。介護福祉関係は、法律が異なるし、死生観については文化が異なる。外国のやり方や方法が、日本にそのまま当てはまるわけがない。日本の緩和医療の源流は結核療養所にあると思われるので、そこに求めるのが良く、外国のホスピスに求めるのは間違いではなかろうか。結核の場合は、病名や病状が徹底して伝えられていたから、患者は病気についても、死ぬ事も含めて知っていた。しかし,がんの患者に真実を知らせなかったので(患者が病気について何も知らなかったという点で)、がん治療から始まった日本の緩和医療のあり方は結核療養所とは大きく異なると考えられる。
人間の生き方や人間生活と自然との調和(ecology)まで含むホスピス運動を、医療という狭い世界に閉じ込めたのが、本邦の緩和医療である。そこに間違いがある。
死の方から生き方を見るのは間違いである。生死に関する事柄は、今日を生きるという視点から、結果としてあちらに逝くがん患者の治療やケアを見直すべきである。お葬式の方法や看取りの方法も世界中で、その国により、その地方により、全く別々なのだから、「死」の方から「生」を見れば、バラバラになってしまう。むしろ、人が「生きる」と言う視点から、死を「生死の繋がり、あるいは生の連続帰着点」と考えて対応した方が良い。
人間も自然に生きる地球上にある生物の一つとして、人間を超える大きなものによって、あらかじめ遺伝子に組み込まれている現象の一つとして「お迎え」も「お知らせ」現象も在る、と考えるのが最も素直で、説明が付く考え方だと思われる。お知らせとは遠くの身内に、夢や予兆など何らかの形で現れて自らの死を知らせるような現象をいう。たとえば親父が夢枕に立ったので、急いで帰省したら亡くなったというようなことである・
また、この度の震災の亘理町の荒浜(あらはま)の被災地に立った時に感じたのは、「合理的にものを考えられる場所も、空間も、時間もない、まるで空襲で爆撃を受けた様な状況」だった。
そこに自分の身を曝したら、「ああ、人間と言うのは大きな存在にぶら下がって生きているんだな。個人が集合すると人間になるんじゃないんだ。実は逆なんじゃないか」と思った。この想いは、考えて、得たものではない。ふっと湧いてきた。「あそうか!」と体にストンと落ちてきた。あの場では、物を考えるはずの自我そのものが破綻していた。破綻した時に何が人間の心を支えられたのか、と言ったら、人間とは大きな命に繋がっているもんなんだ。俺が死ぬなんて事は、本当にちっぽけな事なんだ、という様な事が、リアルな感覚として自らの中から湧き出てきた。
これは非常に不思議な感覚だが、被災地に立った多くの人の共通体験でもある。これは集合的無意識論と言うべき現象だと考える。
自分がこのような病気になり、死と対峙する時、人間、病気になって弱ってくると意識が変わる。まず欲求がなくなって、どんどん悪くなるにしたがって植物化する。
体重が強烈に落ちて行く時に、だんだん欲求がなくなって行って、苦痛は無く、生きていたいと言う欲求もなく、いわゆる涅槃に行っちゃう、恐怖も、不安もない。(震災の時に感じた、自分はその一部であると言う)大きな生命体と一緒になっちゃうと言う感覚に近い。死んでいく前に苦痛や恐怖がないというプログラムが人間に組み込まれているとすれば、これは、次の世代に伝達する事はできない(後天的な獲得形質として子孫に伝えることは出来ない)。なぜ、人間に死んでいく前に苦痛や恐怖がないというプログラムがsettingされているんだろう、というと、そこで神様を感じた。
彼は自分の死を前にして感じる事を静かな口調で語りかける。そのことば一つ一つが重く、考えさせられる。
死の臨床における真のホスピスケアを求めて
死の臨床における真のホスピスケアを求めて
私は現在日本死の臨床研究会の顧問をつとめている。日本死の臨床研究会は1977年にスタートした我が国におけるホスピス緩和ケアの最も歴史ある研究会である。その原点は「死の臨床において、患者や家族に対する真の援助の道を全人的立場より研究していくこと」という会の目的にある。2011年度から世話人代表を引き継ぐことになった。
この研究会は約2600名の会員がいる研究会である。年に一度全国大会を行い、北海道から九州まで各ブッロクで支部大会が開催されている。医療関係者だけでなく一般の市民の参加型の研究会であり、学会にしない理由は市民に開けた立ち位置をとり、ひとり一人の「いのち」への向き合いを探求していく学問的研究会を目的としているからである。 医師、看護師、薬剤師、介護福祉士、医療ソーシャルワーカー、僧侶、ボランティア、一般市民など多岐にわたる職種からなる研究会である。
「死の臨床」とは死に直面した時、沸き上がってくる根源的な叫び、すなわち自分のこの世の存在が失われていくという苦悩、言い換えれば不条理な人生を直視したときの深いスピリチュアルぺインの中にある人々への寄り添いだと思う。
スピリチュアルペインとは己の実存の喪失と考える。私たちが生きていく上で最も大切なことは、あるいは生き甲斐とは自分の実存即ちこの世の存在の意味を感じ、生かされている、必要とされていると感じることであると考える。この実存の喪失、生きている意味の喪失こそがスピリチュアルペインだと考える。
ホスピスとは目の前に悩める人にいかに手をさしのべるかという哲学であり、私たち一人ひとりがいただいた「いのち」をその人らしく生ききることであり、医療をはるかに超えた「いのち」の尊厳を大切にすることだと考えている。
すべての人々はその苦悩の中で、その瞬間まで今を生きている。私たちがその専門性を生かし、チームとして患者・家族の皆様の心の架け橋や燈明を照らすことができるかが問われているのだと思う。死の臨床においてすべての人々が自分の人生に意味を見出し、価値を見出して安寧な気持ちで終えていけるようにありたいものである。
私たち一人ひとりは無限の世界からこの世に生を受け、人生を歩み、また無限の世界に戻らざるを得ない。どのような人生を歩もうとも、一人ひとりの人生には必ずキラリと光るものがあり、存在することそのことに意味がある。この二度とない人生をその瞬間まで実存を感じられるような場がとても大切だと思う。ホスピスの場とは悪くて、だめだから行く最期の場ではなく、その瞬間までより良く生きる場であり、それを支え、橋渡しをする場である。そのために、時間と空間がとても大切な場であり、いのちを通じて生きるということを考え、学ぶ場だと思う。病院でもホスピス緩和ケア病棟でも住み慣れた我が家でも患者さんとそのご家族が安心して最期まで過ごせることが大切なのだと思う。
そして、看取りとはその人が歩んだ全人生を看取ることであり、その看取りが出来るのは共に歩んだ家族や親族や友人などだと思いう。最期のいのちは家族にお返ししなければいけない。第35回死の臨床研究会の大会長の蘆野・長澤両会長がご挨拶の中で「学びの場である看取りを、非日常性の医療の場から日常の生活の場、あるいは日常的な環境になるように配慮した場に移すこと、医療者ではなく家族や親族あるいは友人などが看取るように配慮すること、地域社会が看取りを支援することが、今重要であると考えます」と言われている。この研究会の原点だと思う。
がん対策基本法に基づき、国民に広く緩和ケアの普及・啓発がなされ、医療的な面では進歩し続けている。しかし、金城学院大学学長の柏木先生のいわれる人の死は医学的出来事ではなく、人間学的出来事であり、社会学的出来事であるということである。
医療の進歩に伴い多くの恩恵がもたらされているが、人の死は決して医療では救えない。この世の存在は医療とか人間の力では及ばないことに気づかなければいけない。現代医療のアンチテーゼとして死の臨床研究会が産声を上げた原点を噛み締めなければいけないと考える。
今後、我が国を取り巻く環境はますます複雑化してきている。少子高齢化の中で、多死社会の中で一人ひとりの人生の生き方や終え方の価値観も変化し、多様化してくる。
医療、看護、介護、福祉の現場で、一人ひとりのいのちを大切にする智恵と工夫がますます重要になってくる。日本死の臨床研究会がなすべき役割は現場の実践を生かし、実践活動の学びの場となり、広い視野にたって益々発展していく事が大切であると考える。
死とは忌み嫌うものではなく、人生をやり終えた、あるいは自分の人生に納得し、後に託し、安寧な気持ちで終えていくという温かいものでなければいけないと考える。そんな生き方がとても大切だと思う。
今日も病棟で若い30代の若者が意識無く、ケアを受けている。その奥様と二人の小さな子どもたちがそばで過ごされ、普通の生活の営みがなされている。子どもは幼稚園にも病室から通っている。ここが家なのである。そこにはいのちの息吹が感じられる。いのちがとても愛おしく、ここに存在することに意味があるのである。私たちは今、ここに存在していることがすばらしいことに気づかなければいけない。
緩和ケアの取り組みとホスピスのこころ
緩和ケアの取り組みとホスピスのこころ
山口県のホスピス緩和ケアの歴史は1990年「がんと末期医療を考える会」が発足し、主宰の岡博氏が自らのがんの闘病を通じて「末期医療の充実とは何か。一言で言って人間の死を尊重してくれるということだ。現在、病院でいったい何人の人々がよく生き得、良く死に得ているでしょうか。懸命に生きてきた人生の場所が昭和二十三年の基準によるわずか二、六畳というベッド空間。プライバシーは全く認められず、他の患者の鼾やおなら、時には糞尿の臭い、同室者との人間関係を保つための妥協や追従。なに一つ思うようにならず、家族は肩身狭く付き添う病院の大部屋であるとは!」との訴えに触発され、私たちが院内に「ターミナルケア研究会」を設立したのがスタートです。1992年には県内で初めての3床の緩和ケア病床を設置し、本格的に取り組み始めました。その後、東病棟の建設に伴い、最上階に25床の承認施設としての緩和ケア病棟を1999年11月にスタートすることができました。日本赤十字社93病院の中で初めての緩和ケア病棟でした。開設記念講演に柏木哲夫先生に来ていただき、10周年開設記念に再び柏木先生にお出でいただくことができ、本当に嬉しく思います。1992年の緩和ケア病床をスタートした時点から我が家で最期を過ごしたいという患者の希望に添って、在宅ホスピスケアも行ってきました。患者さんやご家族が安心して過ごせる療養の場を提供するべき、入院,在宅,外来を三位一体としてシステム化することが大切であると考えて行動してきました。その結果、全国に先駆け山口市の行政の力を借りて2003年に山口市在宅緩和ケア推進事業を開始し、年齢制限なく1割の自己負担で福祉サービスが受けられる体制を造ってきました。その後、2004年山口市在宅緩和ケア支援センター開始。笹川医学医療研究財団ホスピスナース研修施設となり、2007年には日本医療機能評価機構付加機能評価緩和ケア機能認定を受けました。また、山口県在宅緩和ケア対策推進事業開始に伴い、山口県在宅緩和ケア支援センターを設置、2008年院内緩和ケアチームを開始しました。
このような歴史を振り返ってみて、何も無いところからスタートして苦節20年、感慨無量です。振り返ってみるに軌跡はあとから出来て来ることをつくづく感じます。いつも物事は成就出来るという信念のもとで歩み続けてまいりました。
今一番心配しておりますことはホスピスが次第に医療化していく我が国の現状をかんがみ、今一度ホスピスの意味を問い直さなければいけないと痛感しています。
ホスピス・緩和ケア病棟がスタートしたのは現代の病院死の中での人の死の尊厳があまりにもおろそかにされてきた経緯の中で、あるいは人の死の医学化の中で、身体的な生命のみに重きをおき、「いのち」としてのトータルケアを失ったことへのアンチテーゼとしてスタートしているのです。
良く考えてみるに私たちは天命をいただいているのです。すべての医療行為は延命のために行われ、天命を全うするためになされているのです。しかし、私たちがいただいたこの世の存在は医療や人間の力のおよばない世界であることに気づかなければいけません。
ホスピスの本質は目の前に悩める人にいかに手をさしのべるかという哲学であり、私たち一人一人がいただいた「いのち」をその人らしく生ききることであり、医療をはるかに超えた「いのち」の尊厳を大切にすることです。「死を看取る」ことは「生きること」を学ぶことであり、無限な世界からいただいたこの世の有限な「いのち」がふたたび無限の世界へ還って行くことへの場の提供です。人間存在における苦悩は生死(しょうじ)の世界に直面して沸き上がってくる根源的な叫びにたいして、内なる世界すなわち自分の生きてきた人生に意味、価値があることに気づき、その瞬間まで生きていることの喜びを感じるとともに、絶対世界すなわち大いなる力にゆだね、安寧な気持ちでこの世を終えていけるような架け橋の場がホスピスなのです。身体症状緩和は必要条件であり、ライセンスを持つ医療従事者は義務なのです。しかし、ホスピスの求められているのは生死(しょうじ)の世界への対応であり、悩める人に燈明(とうみょう)を照らすことであると思います。そのためにも医療従事者は自らの死生観,人生観などをしっかり築いていかなければいけないと考えます。
ホスピス・緩和ケアのこころ
ホスピス・緩和ケアのこころ
多くの人びとが生命を脅かす疾患に直面したとき、患者さんもご家族も同じ苦しみに見舞われます。特にがんと診断されたときから、患者さんもご家族も心はゆらぎの連続です。がんの進行や再発の不安を抱えながら、希望を見いだしたいと思いながら、日々の療養を続けておられます。身体的な苦しみがあると希望は見いだされなくなります。また、ご家族のこと経済的なことにも思い悩まれます。ご家族もその苦しみは同じなのです。治ってほしい、元気でいてほしいと願い続けられます。そして、スピリチュアル、魂のさけびがいつも不安となって頭をもたげてきます。いつまで生きられるのだろうかという将来への希望が見いだせなくなり、愛する家族や人生をともに歩んだ人と別れなければならないという不安、そして自分で自分のことができなくなり、この世にいただいた「いのちの存在」そのものに向きあわざるをえなくなります。その時私たちは何ができるのでしょうか。悩まれ苦しみにある患者さんやご家族の方の足下にそっと灯りをかざすことではないでしょうか。温かい心の通い合いであり、患者さんとご家族の不安に寄り添い、薄明るい歩むべき道筋が見えてくるように傍らに立つことではないでしょうか。ホスピスは悪くて、だめだから行く最後の場ではなく、その瞬間までより良く生きる場であり、患者さんとご家族を支え、橋渡しをする場であると思います。辛さを受け入れていくことはとても時間がかかります。一つ一つの希望が少しずつ削ぎ落とされていきます。これを自分で受け止めて行くにはとても時間がかかります。受け入れられなく、諦めになっていくことも多くあります。患者さんの苦しみに寄り添われるご家族には共に過ごす時間と空間がとても大切な場になるのです。ご家族の悲嘆が大きくならないように患者さんとご家族のこころの架け橋がとても大切だと思います。そして、ホスピスの場は患者さんがその瞬間まで生ききられ、寄り添われる家族はそのいのちを通じて生きるということを考え、乗り越えて、いただいた自らのいのちを生きるということを学ばれる場だと思います。そして、患者さんやご家族が辛いときに辛いと言え、孤独にしないように寄り添って行くことが問われていると思います。その瞬間まで自分のいただいた人生に意味を見いだされ、納得できるように、また安心して後に託すことができるような寄り添いと架け橋を大切にした、そのようなホスピスでありたいと思います。
在宅の良さは医療目線にならない、生活の中での存在であり、管理からの脱却であると考えます。多くのチームの協働により、患者・家族に寄り添い、生きる希望を見出し、その瞬間まで自立を支援し、皆様の尊厳性を大切にした関わりだと思います。2次元の世界から3次元の世界へ、ベッドから屋内へそして屋外へ、生活空間を広げ、今ここに生きているということを感じ、天の恵みの中で、家族の愛の中で、多くのチームの協働の中でその瞬間まで実存を感じ、ゆっくりした時間の中でいのちを見つめ合う事ができていくのです。在宅ケアは人間らしく生きるということの最も大切な希望につながる支援だと思います。
サロンイベント
カレンダー
診療所のサロンにおいて予定している行事です。
サロンイベント
カレンダー
診療所のサロンにおいて予定している行事です。
サロンイベント
カレンダー
診療所のサロンにおいて予定している行事です。
アクセス
〒 753-0044
山口県山口市鰐石町1−12
TEL:083-902-5300
FAX:083-902-5303
アクセス
〒 753-0044
山口県山口市鰐石町1−12
TEL:083-902-5300
FAX:083-902-5303
アクセス
〒 753-0044
山口県山口市鰐石町1−12
TEL:083-902-5300
FAX:083-902-5303
リンク
リンク



